新鮮でしかも盗作の感じがしない簡素なメロディをつくることほど難しいことはない。
バート・バカラックの言葉です。この一言に、彼の作曲における芸術的指向が現れています。クラシック音楽の作曲家は、まさにこの、バカラックの一言に込められた思いで、作曲してきました。ベートーベンはモーツァルトという巨大な壁を超えるために、憧れの中にもそれを超克しようともがき、またベートーベンがそうして打ち立てたこれまた大きな壁に、その後の作曲家も苦しめられる。こうした結果、クラシック音楽は、どんどんと複雑に、新しいものへと生まれ変わることとなりました。過去の偉大な作品に渡り合うには、何かこれまでとは“変わったこと”をしなければなりません。
番組では、解説者の栗山和樹さんが、バカラックの音楽には“変わった”ところがたくさんあることを指摘しました。具体的に、ミュージカル音楽の《プロミセス・プロミセス》やディオンヌ・ワーウィックが歌った《サン・ホセへの道》を引き合いに出し、拍の取りにくい“変拍子”や、楽節のユニークさ、コードの複雑さを説明していました。後者《サン・ホセへの道》では、普通の音楽では4小節でひとまとまりになるところを、1小節を加え5小節でひとまとまりにした面白さを語っています。こうした楽節の加減は、バカラックの曲には多く表れます。普通に聞いていると気づきませんが、実は名曲《雨にぬれても》にも、楽節の追加が行われている箇所があります。“変わったこと”を自然に聞こえるように行うところに、バカラックの天才性が垣間見えます。ちなみに、簡素な曲になりがちなところに、楽節を加減することで独自のものにしていく技法は、マーラーも《交響曲第6番》の第3楽章の主題に用いたりと、特に19世紀末~20世紀前半のクラシック作曲家にもよく見られます。
バカラックの師匠たち
先に述べたように、バカラックは若いころビバップにのめりこみ、それと同時にラヴェルの《ダフニスとクロエ》に心酔しました。小さいころからピアノを習っていたバカラックですが、今まで知っていたベートーベンやワーグナーなどのクラシック音楽とはまた違った世界を《ダフニスとクロエ》の中に感じ、バカラックは音楽大学に通いました。音大ではミヨーやマルティヌー、カウエルといった、20世紀の大巨匠たちに指導を受けています。特にミヨーとの出会いは大きく、無調音楽がクラシック音楽の主流だった当時において「口ずさめるメロディーを書くことを恐れるな」という激励を受けることとなりました。ミヨー自身、《スカラムーシュ》など、ジャズなどの大衆音楽の要素を取り入れ、非常に親しみやすい作品を書いていましたので、その存在自体がバカラックにとっては大きな後ろ盾になっていたことでしょう。
アメリカの作曲家、カウエルは、バカラックの師匠の3人の中ではもっとも前衛的ともいえる作曲家。トーンクラスターやピアノの内部奏法など、新しさを突き詰めました。しかし、調性的なアプローチも多くの楽曲に取り入れ、《3つのアイルランドの伝説》では、トーンクラスターの中にも五音音階を主軸とした民謡の雰囲気を残しており、また内部奏法の名曲《エオリアン・ハープ》は明らかに美しいコードが鳴ります。
もう一人の師、マルティヌーは、6つの交響曲が有名な作曲家。特にその第6番は《交響的幻想曲》と名付けられており、演奏の機会も多いです。
この3人の師に習ったバカラックは、芸術的な音楽技術も吸収しつつ、シェーンベルクを中心とする当時の“芸術音楽”とは距離を置き、ポピュラーミュージックの道へ進みました。もしバカラックが、バリバリの現代音楽作曲家になっていたら、《雨にぬれても》や《遥かなる影》などの名曲が聴けなかったと思うと、調性音楽に寛容なこの3人の師に感謝の念がこみ上げます。
参考文献:小沼純一『バカラック、ルグラン、ジョビン―愛すべき音楽家たちの贈り物』2002年 平凡社
吉田秀和『マーラー』2011年 河出書房新社
(文・一色萌生)

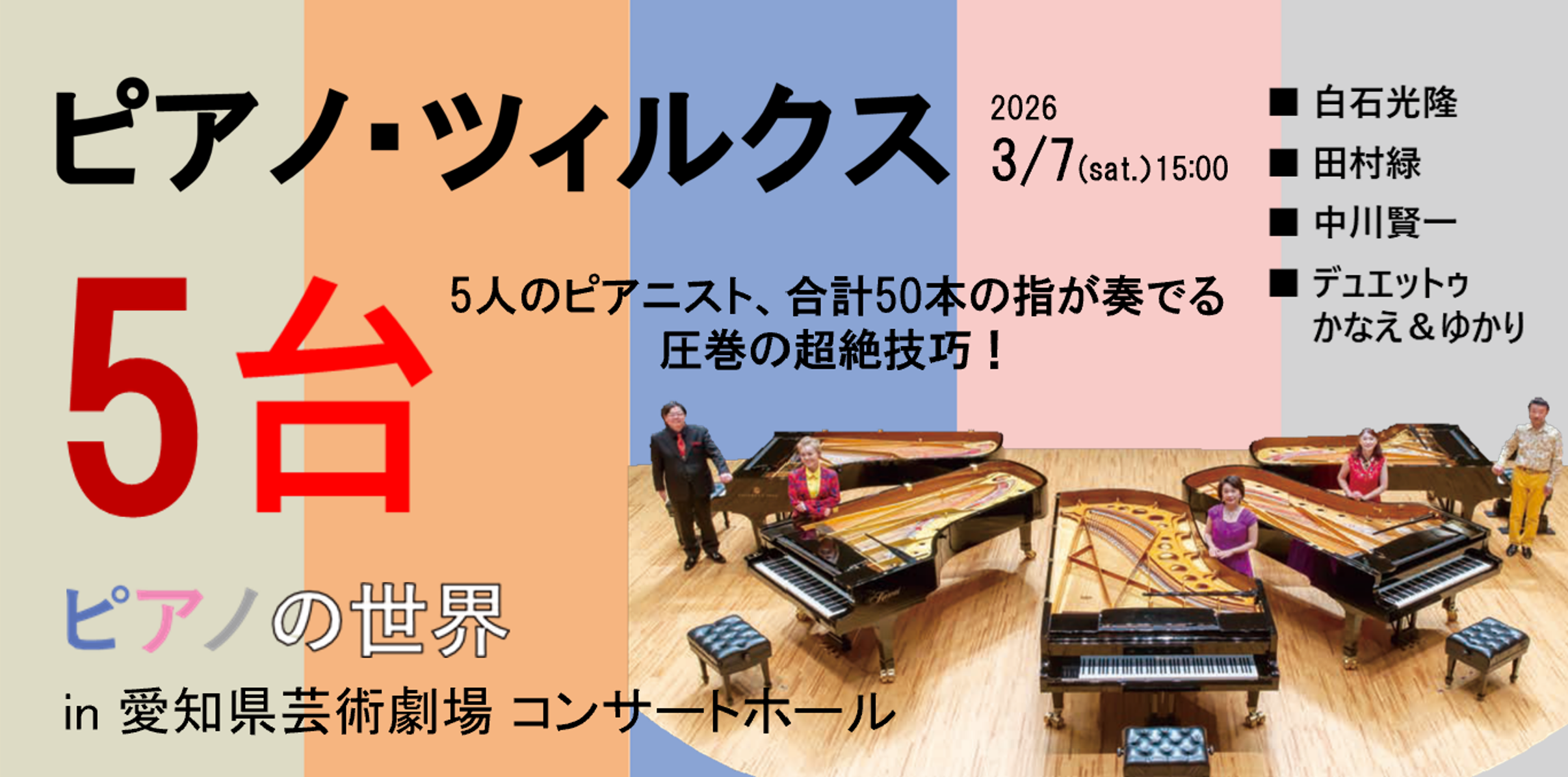




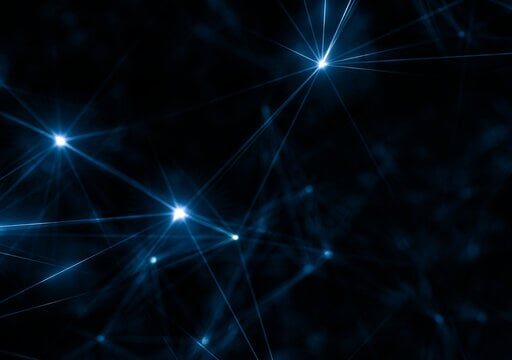









©入り.png)







C福岡諒祠-512x512.jpg)






























