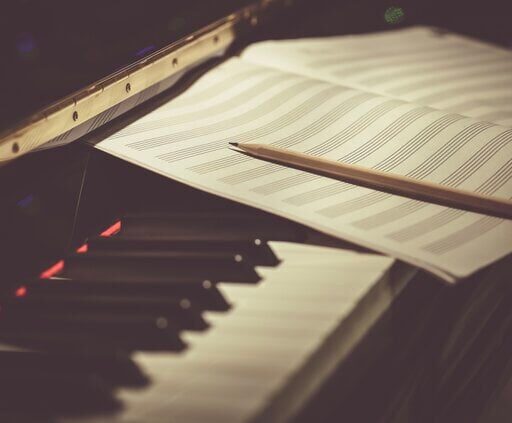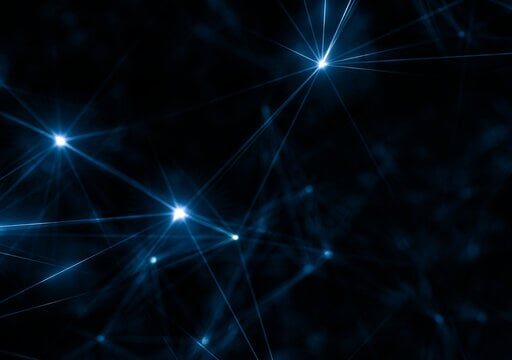ラグタイム

ニューオーリンズの街での様子
ジャズ発祥の地ニューオーリンズでラグタイムが演奏されるようになった19世紀末は、出版された印刷楽譜を購入し家庭で演奏を楽しむ市民アマチュア音楽家が増えた時期でもあります。バンドマンの移動でアメリカ国内に普及したジャズは、次いでアメリカで出版されたラグタイムのピアノ譜が輸入されヨーロッパでも流行しました。これは、フランスに留学することが多かった、ニューオーリンズの市民権を持つクレオールの商人子弟たちが一翼を担っていたからかもしれません。
20世紀の初頭、アマチュアたちの熱を集めるジャズにドビュッシーも反応します。彼は、ラグタイム・ベースとクラスターとで裏拍を目立たせたダンス音楽を連想させる作品「ゴリウォーグのケークウォーク」(ピアノ組曲《子供の領分》第6曲、1906〜08年)や、「ミンストレル」(《前奏曲集第1集》(1909〜10年)、「風変わりなラヴィーヌ将軍」(《前奏曲集第2集》1910〜12年)などを作曲し、その革新的な不協和音の使い方は、クラシックだけでなく後のジャズピアノに影響を与えました。ドビュッシーはジャズに傾倒した作家コクトーと親交が深く、一方で犬猿の仲だったサティも「ラグタイム」(バレエ《パラード》1917年)を書いていますね。ストラヴィンスキーもジャズのリズムやラグタイムの音型にインスパイアされた《ラグタイム》(1918年)と《ピアノ・ラグ・ミュージック》(1919年)を残しています。
ブルース
番組ではブルーノートスケールの説明もありました。外国へ旅することが多かったミヨーは、ロンドンでジャズバンドの生演奏と出会い、魅了されたままアメリカまで渡ります。ジャズの文法、リズムと音色を取り憑かれたように追い求め、ニューヨークのハーレム地区で演奏するジャズマンたちとの交流の果てに書かれたのが、バレエ《世界の創造》(1923年)。旋律と和声にブルースらしさが表現されています。次いで、ブルーノートに強い反応を見せたのはラヴェルです。彼はラグタイムにインスパイアされたオペラ《子供と魔法》(1925年)も残しましたが、ブルーノートは《ヴァイオリン・ソナタ》(1923〜27年)第2楽章「ブルース」、《左手のためのピアノ協奏曲》(1929〜30年)の中間部(Lento)、そして《ピアノ協奏曲ト長調》(1929〜31年)の第1楽章などに真摯に取り入れられています。1928年にアメリカとカナダでの4ヶ月に及ぶコンサートツアーを行った際、ジャズや民族音楽の要素を取り入れた彼の音楽はアメリカの音楽界から高く評価されました。特にオーケストレーションに関しては、《ラプソディ・イン・ブルー》(1924年)で「オーケストラの使い方が不慣れ」と評されたガーシュウィンが師事を乞うほどだったとか。帰国後に着手した2つの協奏曲には、ツアー前より黒人霊歌やアメリカでの音風景が色濃く残っています。
参考文献:
「The Decline of Improvisation in Western Art Music: An Interpretation of Change」Robin Moore, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music Vol. 23, No. 1 (Jun., 1992)
「French Music and Jazz in Conversation: From Debussy to Brubeck」Deborah Mawer, Cambridge University Press, 2014
「The history and development of jazz piano : a new perspective for educators.」Billy Taylor, University of Massachusetts Amherst, 1975
「The respective influence of jazz and classical music on each other, the evolution of third stream and…
」Liesa Karen Norman, The University of British Columbia, 2002
「作曲の科学 : 美しい音楽を生み出す「理論」と「法則」」フランソワ・デュボワ著 ; 木村彩訳、(ブルーバックス, B-2111)講談社, 2019
(文・武谷あい子)