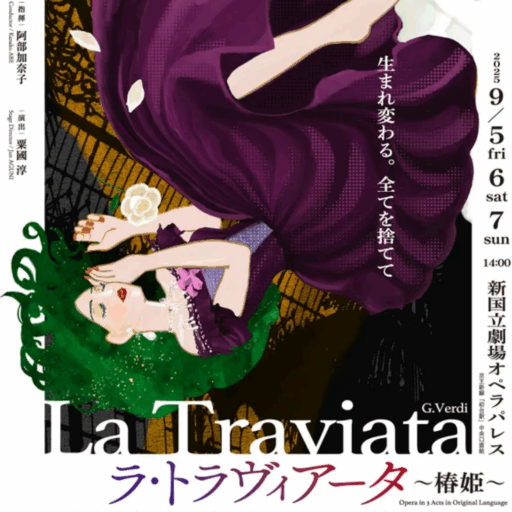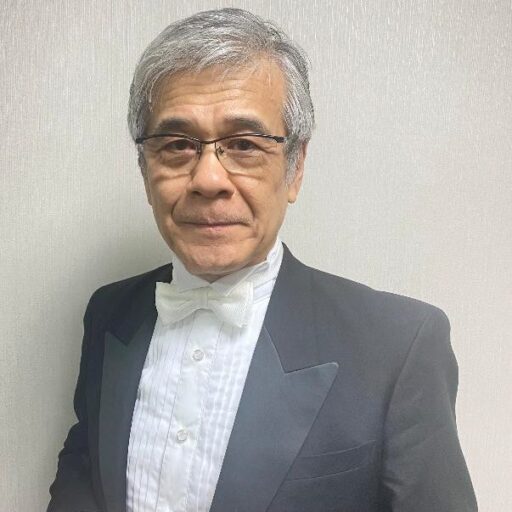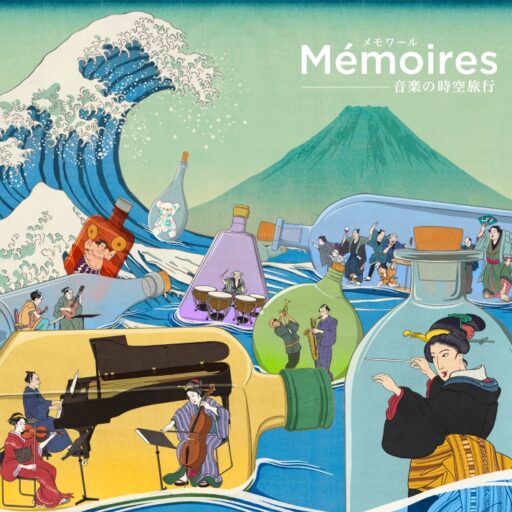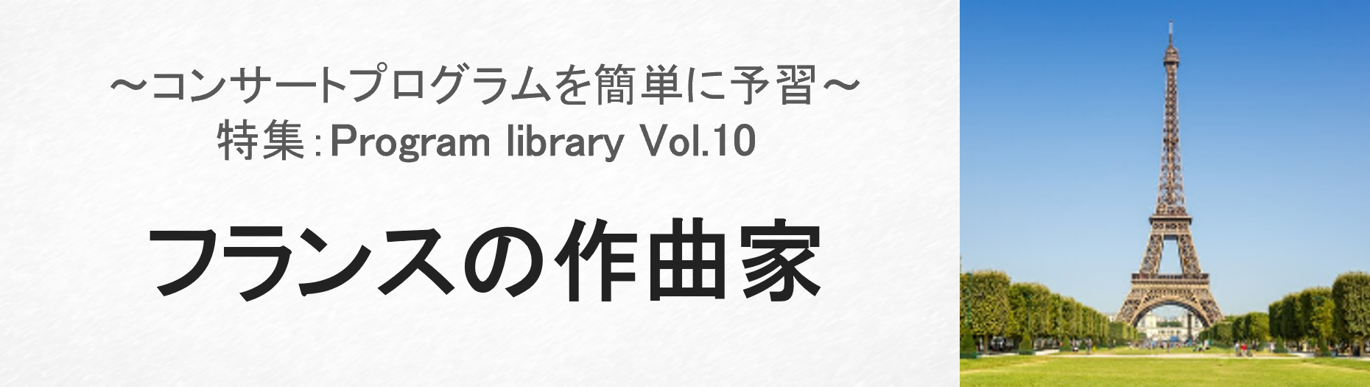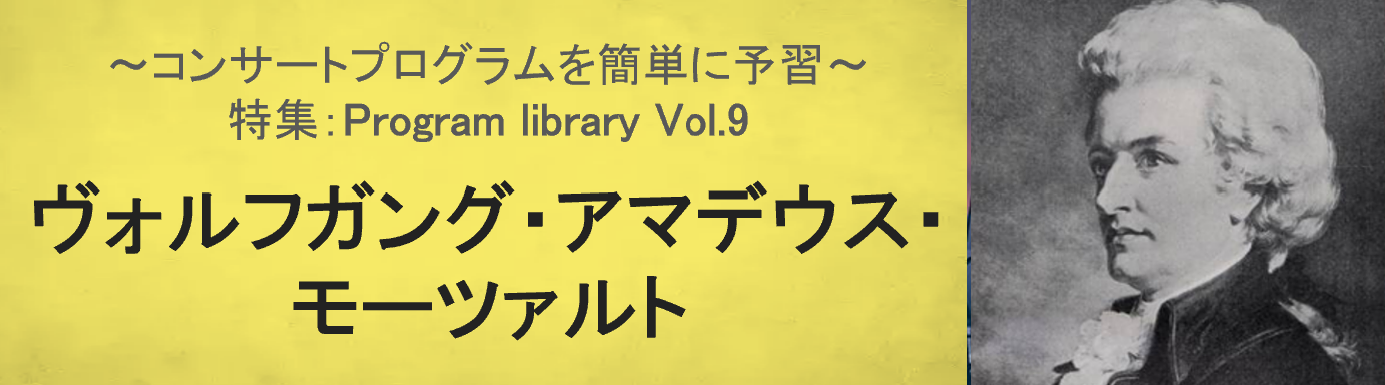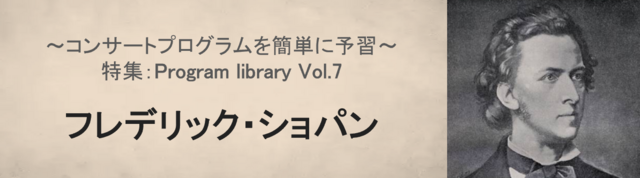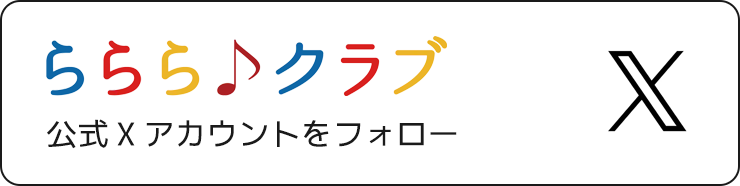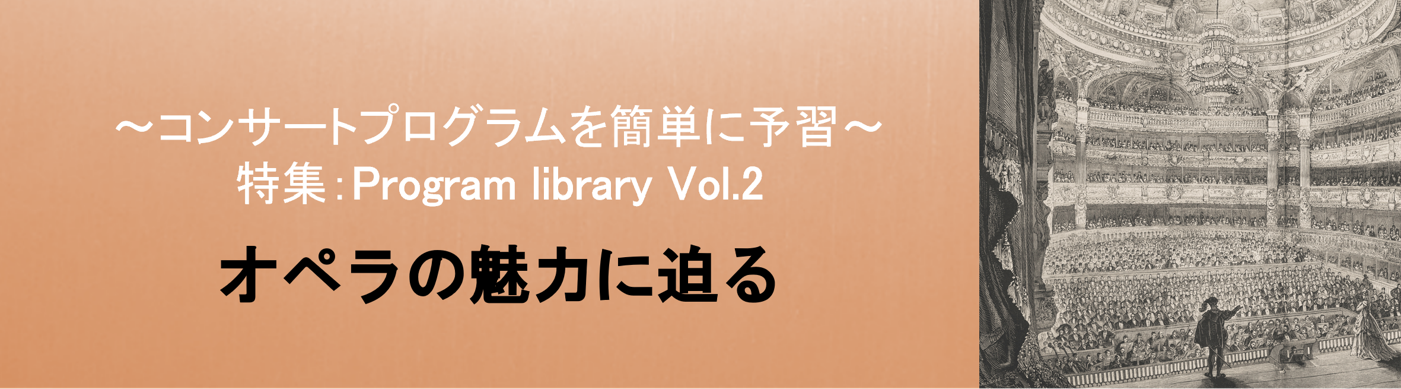10代のころから国内をはじめ、フランスで開催されたフルート奏者にとって最も権威の高い「ジャン=ピエール・ランパル国際フルートコンクール」での優勝など、世界中で実力を認められているフルート奏者・上野星矢さん。“いまもっとも忙しいフルーティスト”と言っても過言ではなく、演奏会での引っ張りだこをはじめ、コロナ禍以降はオンラインでのコンクールや、プロと愛好家が同じ舞台に立つコンサートの主催といった、フルートの魅力を伝える教育者としても邁進されています。
音楽に囲まれた幼少期からプロとして教えることの意義、ご家族と過ごす時間など、たっぷりお話をうかがいました。
家族の歌声にかこまれた幼少期と、フルートとの出会い
―― 上野さんは小さいころから音楽や芸術に触れ合うことが多かったのでしょうか。
母は声楽家で父は演劇をしているので、おそらく生まれたときから音楽や芸術が身近にあったのだと思います。物心がついてから覚えている一番古い音楽の記憶は、母がコンサートで歌っている姿です。わたしはまだホールの座席で長時間聴けるような年齢ではなかったので、ロビーのソファーでモニターから聞こえてくる音を耳にしながら遊んでいた記憶があります。
また、姉も声楽家なんです。その姉が小学生から高校生まで東京放送児童合唱団(現NHK東京児童合唱団)に入っていて、歌番組の撮影に出かけたりしていました。合唱団のコンサートを聴きに行ったのもよく記憶に残っています。そこで初めてハーモニーを奏でること、和音の美しさに気がつきました。
―― フルートを始めたのは小学4年生のときだったそうですね。
家庭内で音楽を耳にする環境には恵まれていたのですが、わたし自身がなにかをしたいと思ったことは、実はなくて。両親も特に「何かをやりなさい」ということもなく育ちました。
通っていた小学校では4年生になるとクラブ活動ができるようになるのですが、たまたまその年に、吹奏楽界ではカリスマ的存在の原悠三先生が転任されてきました。原先生の噂を聞いて吹奏楽部の見学に行ったときに、先生の指揮や先輩たちがかっこよく演奏する姿に圧倒されて入部したのが、フルートを始めたきっかけです。

―― 始めたころの思い出はありますか?
練習を始めた当初は楽譜が読めなかったので、苦労した記憶があります。先生から手ほどきを受けて指使いを覚えていくのですが、紙の運指表を見て吹いて「今この指使いで吹いたら、このくらいの高さの音が出た」みたいな、完全に感覚のみで覚えていきました。だんだんいろんな音が出てくるようになったのはすごくうれしかったのですが、最初は大変でした。
中学生になるとコンクールに出るようになりましたが、中学1年生で初めて全日本学生音楽コンクールに出たときは、これまでで一番印象に残っています。いや印象に残ったというより、舞台上で一番緊張した体験ですが、目の前が真っ白になりました。吹いている心地もないし、気がついたら終わっていました(笑)。
いまの演奏活動にも生きる留学時代の経験
―― 2008年に「第8回ジャン=ピエール・ランパル国際フルートコンクール」で優勝した翌年、大学2年生からはフランスのパリ国立高等音楽院へ留学されたそうですね。
当時は留学1か国目ということもあり、「外国語を話して生活していけるのだろうか」などの不安や緊張が強かったです。生まれも育ちも東京で、ひとり暮らしもしたことがなかったので。でも3か月くらいで言葉も習得できたし、自分のペースで過ごせるようになったのはすごく自信になりましたね。
音楽的なことに関しては、そこまで違和感を感じずにスッと馴染むことができました。まわりの学生も世界中から来ていたので、色々な国の方と接して、刺激のシャワーをずっと浴び続けているような感覚でした。
―― パリで師事されたソフィー・シェリエさんは現代音楽演奏のイメージが強いですが、上野さんも現代音楽を中心に学ばれたのでしょうか。
いえ、パリではいままで日本で習ってきたことなどもすべてリセットするつもりでした。フルートの構え方から、呼吸法・発音の仕方も学び直すつもりで教えてくださいと先生にお願いしたのです。
現代曲ももちろんやりましたが、バロックから古典・ロマン派・近現代にいたるまで、すべての時代のレパートリーを見ていただきました。
―― なかでも思い出深いレッスンはありますか?
当時はそれぞれの生徒の実力をさらに引き上げるため、先生のレッスンもかなり厳しかったように思います。わたしは毎週必ず新しい曲を練習して持ってくるように課されていました。パガニーニの《24の奇想曲》フルート版を、毎週1曲ずつ譜読みして持っていったり。
あるとき、譜読みが間に合わなかったんです。でも、なんとかなるだろうと思ってレッスンに行ったら、最初の4小節ぐらいで楽譜を閉じられて。「また来週」って言われて終わりました(苦笑)。
―― 厳しい……(笑)。そうすると常にフルートや演奏のことを考えなければなりませんよね。
そうですね。そういう世界で過ごしていたので、気を抜く時間はなかったです。いつもどの時間に練習するかを考えていました。厳しい環境でしたが、確実にいまの人生のなかで役に立っている貴重な体験だったので、とても感謝しています。
―― フランス留学後はさらにドイツでも学ばれていたそうですね。
フランスでは3年間かなり濃密な時間を先生方と過ごしたので、大学院はほかの国に行ってみてもいいんじゃないかという相談の上で、ドイツに留学しました。
―― 当時は唇の不調があったとのことですが、どうやって向き合われたのでしょうか。
国が違えばやはり文化や話す言葉も違うので、フルートの演奏法にも違いがあります。それは日本からフランスに行ったときにも思いましたが、1回自分の中でリセットボタンを押して奏法を学び直そうという心持ちでやったため、フランスでは上手くいったんです。
ドイツに行ったときも、自分が学んだことをミックスして、自分にしかできないものを作ることを最終目標にしていました。でも、せっかくドイツに来たんだから、その先生の提唱する奏法を学びたいと思い再びリセットボタンを押しましたが、失敗しました。
―― 失敗したというと……?
失敗したというか、自分の理解の仕方などが未熟だったのだと思います。無理に奏法を作ってしまったので、それがあまり良くない方向に向かっていって。
単純に話すと、演奏法の違いを表面的な部分だけで見ていた自分がいました。身体の内部は見ることができない―― それが一番難しいところなのですが、管楽器の演奏において、一番大切な呼吸や構え方への意識を忘れてしまった。結果、負荷がかかりすぎて唇のコントロールがまったく効かなくなり、思うような演奏や表現が難しくなってしまいました。その経験から、フルートの演奏の技術の8割ぐらいは呼吸や構え方にあるのではないかと思うようになりました。
また、フランスにいたころに国際コンクールなどをたくさん受けて成績が出ていたので、自分としてはすごく自信がある状態でドイツに行きました。もちろんドイツで師事したアンドレア・リーバークネヒト先生も、わたしの音楽を100%評価してくださった状態でレッスンが始まったのですが、先生の要求に応えていくことがうまくできないと感じたときもありました。
しかし、このような経験もあるからこそ、当時先生にアドバイスいただいてできなかったことも、いまになって「あれはこういうことだったのか」と分かるようになりました。いまだにレッスンを受けているような感覚で過ごしています。

教わるから教えるへ―― プロと愛好家の交流を大切にする教育活動
―― 現在は教える活動にも注力されていますね。上野さんはプロの奏者とフルート愛好家の交流の場を大切にされている印象ですが、その意義はなんでしょうか?
実体験として、子どものころにレッスンで「先生の音すごく綺麗だなぁ」「あんな音で吹いてみたいなぁ」と思っていました。
やっぱり近くで先生が吹いてくれたり、自分の憧れている人が一緒に演奏していたりといった体験は、ものすごくモチベーションになります。なので、そういった機会を作りたいなと思って『フルート・セレブレーション』や合宿など、さまざまなイベントを企画しています。
“愛好家の方”が”プロの隣で吹く機会”ってあまりないですよね。ましてや隣でベルリン・フィルの首席が一緒に吹くなんて、ほぼあり得ない話。なので、そういう「あり得ない体験」を自分の力で作ったら、どのくらいみなさんに感動体験をしてもらえるんだろうか……という夢が昔からあったので、それを実現しています。
―― 上野さんのキャリアだからこそ、たくさんのプロの方が協力してくれそうですね。
幸い海外でもいろいろな方と交流があります。いまでもいい関係を持ってお互いに尊敬し合う友人たちで、声をかけるとみなさん快く来日してくださいます。そういうことができる人が日本にどこまでいるかというのは分からないけど、率先してやっていこうと思っています。
―― 教える立場に回ろうとしたきっかけはなんでしょうか?
すばらしい先生方に教えていただいたおかげでいまがあると思っているので、わたしの周りの方に対しても、わたしができること、アドバイスできることをシェアしていきたいという気持ちが一番です。
あとは、わたしの場合は音楽的な環境にかなり恵まれていたのですが、必ずしもフルートをやりたいと思った人の家族が音楽家・芸術家という環境ではないですよね。だから、できるだけすべての人が恵まれた環境になるような世界にするべく、レッスン、合宿やフェスティバルを開催して気軽に参加できるようにしました。そのなかで多くの人にいろんなことを学んでいただけたらなと思います。
家族と過ごす音楽以外の時間も大切に
―― 最近は音楽以外の息抜きの時間はありますか。
結構家族旅行に行くんですよ。家族で出かけるときは楽器も持たず、子どもと遊ぶって感じです。子どもがまだ小さいので軽井沢や熱海など、首都圏からの近場にしか行けないのですが。
―― ご家族と過ごす時間が、音楽とはまた違う時間になっているんですね。
生活していると、やっぱりそこが中心になってきますよね。成長していくのを見るのもうれしいですし。
―― 息抜きの時間も重要ですね。
これまで、自分はどんなに忙しくても大丈夫だろうという自信を持ちながらずっと活動してきたのですが、やっぱり息抜きって大切です。まったく違うことをしながら頭を休めると、ふだん自分が携わっている音楽のことも整理されますね。ずっと同じことを考え続けたり、やり続けたりするというのは良くないんだなと最近思うようになりました。
音楽にしても違うジャンルの音楽、例えばジャズを聴くとか。そういうことが私の中ではとても息抜きになります。
日本全国を駆けめぐるツアーもしたい、今後の活動の展望
―― 今後の活動についてお聞かせください。
いまは大阪音楽大学でも教えていますし、東京では教室も開講しています。あとはフルートフェスティバルの開催やリサイタルやコンツェルトなどの演奏活動と、わりといろんなことをやり尽くしている感がありますが、今後の目標としては、いまやっている活動をより広めて、認知度を上げていきたいです。主催するイベントが「あぁ、あれね!」というレベルで誰もが知っていて、参加したことあるようなものになっていってほしいので、より良いものにしていきたいなと思います。
また、最近はイベントの企画や子育てに重点を置いていたので、今後は自分のリサイタルやツアーにも注力していきたいです。できれば日本全国を一気に駆けめぐるコンサートもやりたいと思っています。
演奏会に出かける特別な時間を楽しむ
―― 演奏会に出かけることも多いかと思いますが、上野さんはどのように楽しんでいますか?
もちろん演奏自体を楽しみに行きますし、その演奏会中の緊張感なども楽しみます。そういった生の緊張感を味わいに行くという意味では、スポーツ観戦に行くのと同じ感覚だと思います。
美しい音楽を聴きに行くこと以上に、“その演奏会に行く”という行動自体を大切にしています。例えば電車に乗って、コンサートホールがある駅に着いて、受付に並んでチケットをもぎってもらうのもひとつの体験ですし。ホールで自分の席を探しているときも、そのすべての体験がコンサートに行く意味なのかなと思います。一瞬一瞬がすごく特別な体験です。
―― フルートの演奏会を聴きに行くとしたら、プレイヤー目線で聴かれるのでしょうか。
時と場合によりますが、プレイヤー目線で聴いています。例えば「この人の技術の詳細を知りたい」というパターン。そういうときはちゃんと観察しないとだから、ロビーでシャンパンを飲んでいる場合じゃない(笑)。
―― ららら♪クラブの読者は、これからもっとクラシック音楽を楽しみたいと思っている方も多いです。そんな読者のみなさんへメッセージをお願いします。
クラシックってよく敷居が高いとか、高貴なものだと思われすぎてしまっているなと感じています。でも、自分が美しいと思うか、自分が楽しいと思うか、それだけでいいんです。コンサートに出かけるということも、特別な体験をして自分が幸せか―― それだけでいいと思うのです。楽しい、美しい、雰囲気が好きといった自分の幸せのため、心を浄化させるために音楽はあると思うので、みなさん自身のために音楽を聴いてほしいなと思います。
<文・取材 山下実紗>

今後の公演情報

| 公演名 | CMGプレミアム イスラエル・チェンバー・プロジェクト Ⅱ |
|---|---|
| 日時 | 6月21日(土) 19:00開演(18:30開場) |
| 会場 | サントリーホール ブルーローズ(小ホール) |
| 出演 |
[ヴァイオリン]ダニエル・バード、小川響子 [ヴィオラ]赤坂智子 [チェロ]ミハル・コールマン [クラリネット]ティビ・ツァイガー [ハープ]シヴァン・マゲン [ピアノ]アサフ・ヴァイスマン [フルート]上野星矢 |
| プログラム |
ドビュッシー:神聖な舞曲と世俗的な舞曲 コーエン:蛍の哀歌 カプレ:幻想的な物語 ベートーヴェン(シャピロ 編曲):交響曲第3番 変ホ長調 Op.55《英雄》(室内アンサンブル用編曲) |
| チケット | 全席指定:7,500円 サイドビュー席6,000円 U25席1,000円 |
| 詳細 | 詳細はこちらから |
| お問い合わせ |
サントリーホール TEL:0570-55-0017 |
上野星矢(Seiya Ueno)
19才で『第8回ランパル国際フルートコンクール』優勝(フランスで開催)。その後、世界を舞台に活躍する日本クラシック界を代表するアーティスト。
東京都出身。小学校4年生でフルートを始め、全日本学生音楽コンクール全国大会中学生の部、高校生の部など、国内の主要コンクールの数々で優勝を果たす。15才で初リサイタルを行い、東京都立芸術高等学校に進学。2008年、東京藝術大学音楽学部フルート専攻入学。同年、世界的フルート奏者の登竜門である『第8回ジャン=ピエール・ランパル国際フルートコンクール』優勝。杉並区文化功労賞受賞。
2009年よりパリに留学し、パリ国立高等音楽院に審査員満場一致で入学。2012年、パリ国立高等音楽院第1課程を審査員満場一致の最優秀賞並びに審査員特別賞を受賞し卒業。2012年10月、日本コロムビアレコードよりファーストアルバム『万華響 KALEIDOSCOPE』でCDデビュー。翌2013年8月にセカンドアルバム『DIGITAL BIRD SUITE』(デジタルバード組曲)を発売し、2作連続で雑誌『レコード芸術』特選盤に選ばれる。2014年、NewYork Young Concert Artist 2014にて最優秀受賞。2015年1月にサードアルバム『into Love』を発売。2014年、ニューヨーク・ヤングアーティスト・コンペティション(NewYork Young Concert Artist 2014)にて最優秀賞。2015年秋には全8か所のアメリカツアーを成功させ、ケネディセンターでのリサイタル、最終公演はニューヨーク・カーネギーホールでリサイタルデビューを果たす。2018年『テレマン:無伴奏フルートによる12の幻想曲』、2019年『W.F.バッハ 2本のフルートのための二重奏曲集』、2022年『フルートによる三大ソナタ』、20232年『フレンチ・コンポーザーズ』の計7枚のCDをリリース。第25回青山音楽賞新人賞受賞、第17回ホテルオークラ音楽賞受賞。
東京交響楽団、チェコフィル八重奏団、イル・ド・フランス国立管弦楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、オーヴェルニュ室内管弦楽団、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、群馬交響楽団、札幌交響楽団、仙台フィルハーモニ管弦楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、パシフィックフィルハーモニア東京、中部フィルハーモニー交響楽団、東京都交響楽団、富士山静岡交響楽団など、国内外のオーケストラと協演。テレビ朝日「報道ステーション」、NHK「ニューイヤーオペラコンサート」、NHKラジオ「きらクラ」「ベストオブクラシック」、NHK「クラシック倶楽部」など、メディアにも度々出演している。2019年より大阪音楽大学准教授。現在はソロリサイタルやオーケストラとの協演などの他、後進の指導など、あらゆる分野にて活躍中。