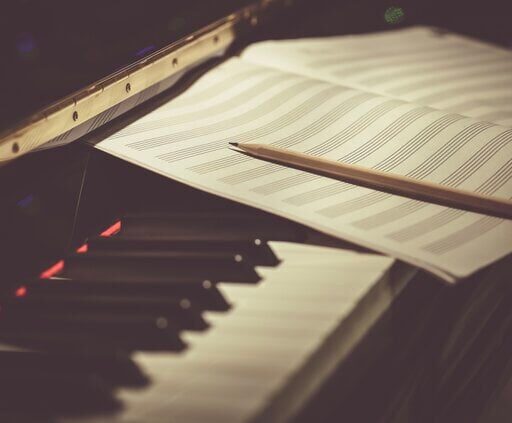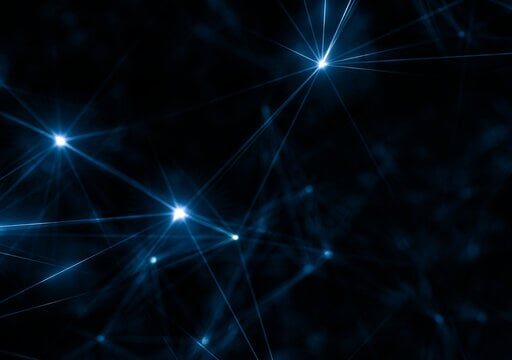絵が上手な作曲家
番組では、絵も上手な作曲家として、メンデルスゾーンが紹介されていました。

メンデルスゾーン『ルツェルンの風景』
銀行家の裕福な家に生まれたメンデルスゾーンは、音楽のみならず絵や語学にも優れていました。旅に行く先々では、音楽のインスピレーションはもちろんのこと、水彩画も残しています。
他にも、20世紀の作曲家、A.シェーンベルクも、絵を描くことを趣味としていました。自画像や弟子ベルクの肖像画、マーラーの葬儀の絵などが残っています。カンディンスキーなど表現主義の画家たちとも親交があり、自身も表現主義的な画風で描いていました。
絵画に触発された音楽作品
ドビュッシーの交響詩《海》は北斎の『富嶽三十六景』の「神奈川沖浪裏」からインスピレーションを得て作曲されました。東洋風の音階を使った波の表現が、北斎の“浮世絵の波”を感じさせます。

ラフマニノフやレーガーに影響を与えたベックリン『死の島
他にも、ラフマニノフの交響詩《死の島》は、ベックリンの同名の絵画(正確にはそのクリンガーの銅版画複製)に霊感を得て作曲されており、レーガーにも《ベックリンによる4つの音詩》という曲があります。また、リストには、番組で紹介されたピアノ曲《伝説》以外に、《死の舞踏》もフレスコ画から着想を得たと言われています。
このように絵画に触発された音楽作品を語ると枚挙にいとまがありませんが、最も有名なのは、ムソルグスキーの組曲《展覧会の絵》でしょう。この作品は、作曲者の友人の画家、ガルトマンの遺作展で見た絵を10枚選んで組曲にしたものといわれています。10枚の絵の他に「プロムナード」と題された部分がいくつかあり、美術展を歩くムソルグスキー自身の心情を表しています。第8曲「カタコンベ」はガルトマンへのレクイエムとしての意味合いが込められていますが、このあとの「プロムナード(死せる言葉による死者への呼びかけ)」では、冒頭では明るかったプロムナードの旋律が、暗く沈んだ形で再現されます。昔、NHKの番組で、この《展覧会の絵》のもとになった絵を、作曲家の團伊玖磨氏が追跡するドキュメンタリーが放送されました。「革命に消えた絵画~追跡・ムソルグスキー『展覧会の絵』」という番組名だったと思います。高校生の時、筆者はこの番組のビデオを見て、《展覧会の絵》に大変興味を持ちました。この番組の内容は書籍化もされていますので、興味を持たれた方は探してみてはいかがでしょうか。
音楽を絵にした画家たち
今度は反対に、音楽に憧れ、音楽を絵にした画家たちを紹介します。
まず、シュルレアリスムの先駆け的なスイスの画家、パウル・クレー。バイオリニストでもあったクレーは、音楽を絵画で表現する、ということで自らの画風を開花させました。ハーモニーやポリフォニーといった音楽表現を、そのまま絵画で表現していました。また、フランスのフォーヴィズムの画家、ラウル・デュフィも、音楽を愛し、楽器のある風景や、作曲家へのオマージュなどを作品に取り入れています。
彼らの活躍したこの19世紀末~20世紀前半という時代、あらゆる分野で活躍する人々が “音楽”に憧れを抱いていました。ニーチェの著作『悲劇の誕生』では、音楽は「最高の芸術形態」と記されており、またヴェルレーヌは『アール・ポエティク』の冒頭に「何よりもまず音楽を」と記しました。“表現主義”など、内からあふれ出る抽象的な何かを求めていた芸術家たちが、最も抽象的な芸術形態である“音楽”を模範とするのは、自然なことのように思えます。これまでの歴史で、絵画を描く音楽はあっても、音楽を描く絵画というものはほとんどありませんでした(楽器を弾いている人の絵などは除く)。これほどまでに“音楽”という表現形態が注目された時代が、かつてあったでしょうか?
ベートーベン・フリーズ -ウィーン世紀末における音楽の優位
こうした中、既存の芸術に反発した若い美術家集団“ウィーン分離派”は、すべての芸術の革新の象徴としてベートーベンを掲げ、作品展を行いました。その中心的な作品が、グスタフ・クリムトの大壁画『ベートーベン・フリーズ』です。

この作品は、第九のもつ“苦悩を突き抜けて歓喜へ至る”という道筋を再現しています。その中には、第九を室内楽アレンジしたマーラーの姿も、聖騎士としてひっそりと描かれています。今でもウィーンのセセッシオン(分離派会館)に行くと、この絵画が見られます。筆者も5年ほど前、実物を見る機会を得ましたが、その時の感動は今でも胸に残っています。
(文・一色萌生)