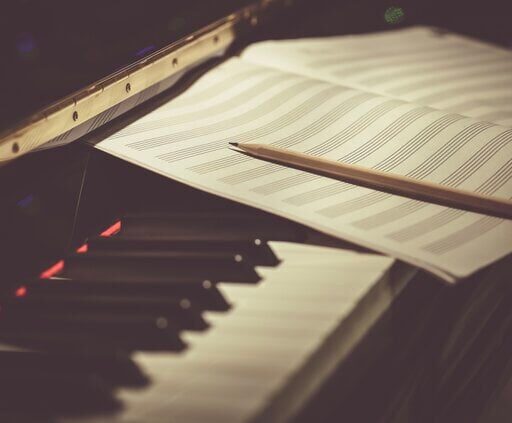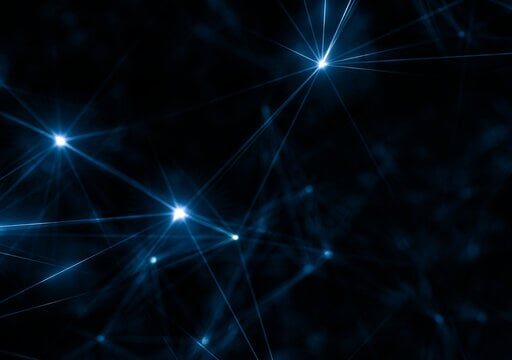10月23日の放送は、「ラモーとバロック・オペラの世界」でした。その中で紹介されたフランスのバロック・オペラ、ラモーの『みやびなインドの国々』から「オーケストレーション」をキーワードとして選んでみました。
「バロック・オペラのオーケストレーション」
オペラというジャンルが生まれるまでオーケストラの呼称も概念も無かったそうです。声楽中心のルネサンスが終わる1600年ごろから、飛躍的に改良されたヴァイオリンを筆頭に各楽器の性能が向上し始め、1700年代には器楽が重要な位置を占めるようになりましたが、それまで楽器編成の決まりもなく、演奏者が弾ける楽器を持ち寄ったにすぎなかったのだとか。定期市でのオペラ興行の伴奏楽団が、ギリシャ演劇での合唱団コロスの定位置オルケストラで演奏することからオーケストラと呼ばれるようになりました。低音声部が一貫して流れる通奏低音の響き、弦楽器の大規模合奏ときらびやかな独奏、軍楽隊から時おり駆り出される管・打楽器が加わるのがバロックのオーケストレーションの特徴です。
「ラモーのオーケストレーション」
ラモーの音楽を聴いて「J.S.バッハと同時代の人間が書いたとは思えない」「おしゃれ」「新しい」といった印象を受ける人は少なくありません。1903年にラモーのオペラを聴いたドビュッシーも同様だったようです。シンプルな構成、和声が導く明るく美しくキャッチーなメロディーとリズム。しかし、それだけではないのです。今日では常識となった強弱のグラデーション、不協和音+音階の急速演奏+トレモロによる「地震」の音響表現、そしてティンパニのパート独奏起用。オーケストラの概念が固まっていない時期にこれだけの発明を遂げたラモーの音楽は、100年先の世界でもまだ「新しい」と言われ続けるかもしれませんね。
参考文献:「The Birth of the Orchestra, History of an Institution, 1650-1815」
(文・武谷あい子)