
ベートーベンが切り開いた新しい“交響曲”の形
“交響曲”は、オーケストラ音楽の中でも、その作曲家が持てる力の全てを注いで心血を込めて作った、まさに至高の芸術ジャンルです。“交響曲”がいつからこんなに大層なものになったかというと、まさにベートーベンからです。ベートーベンは、ピアノ・ソナタや、弦楽四重奏曲などで実験したことを、集大成として交響曲へと取り入れました。1曲1曲が異なる個性を持ち、あらゆる方面で音楽に変革をもたらしたのです。以降の作曲家は常にベートーベンの敢然と輝く9曲を意識して交響曲に挑むこととなりました。これから、その9曲の交響曲をそれぞれ簡単に紹介していきます。
交響曲第1番ハ長調 Op.21
ハイドンやモーツァルトを踏襲した古典的な交響曲です。しかし、属七の和音で始まったり、第3楽章にスケルツォ(メヌエットと表記されているが実質的にはスケルツォ)が置かれていたり等、すでに革新的な意図が感じられます。
交響曲第2番ニ長調 Op.36
第1楽章の序奏ではすでに第九を彷彿とさせる箇所があります。アレグロになってからは、非常に推進力のある音楽で突き進んでいきます。この作品から、舞踏楽章は完全に“スケルツォ”と表記されるようになります。
交響曲第3番変ホ長調「英雄」 Op.55
当時長くても30分程度だった交響曲というジャンルですが、いきなり50分を超える大曲です。音楽の内容も非常に壮大でドラマ性を持ち、この曲から“ロマン派”が始まったとも言えます。楽器の扱い方も革新的で、ホルンを朗々と歌わせる様は、すでに後期ロマン派を思わせます。
交響曲第4番変ロ長調 Op.60
英雄と運命に挟まれて、「2人の巨人の間に挟まれたギリシアの乙女」などと形容されますが、曲調は勇ましく、勢いのある堂々としたものです。カルロス・クライバーが演奏して以降、急速に演奏されることも多く、第1楽章や第4楽章は、さながら運動会のよう。
交響曲第5番ハ短調「運命」 Op.67
言わずと知れた、交響曲の王様です。なぜ王様なのかと言えば、冒頭の有名な4音のモチーフが全曲を支配し、無駄を一切排した、音楽構成・構造の面で完璧な形だからです。一方でドラマ性も感じられ、第3楽章から続けて第4楽章へ至る高揚や、しつこいほど畳みかけるような終結部などは、聴く人の感情を大きく揺さぶります。また、楽器も大幅に拡充され、第4楽章では当時は教会楽器であった3本のトロンボーンや、ピッコロ、コントラ・ファゴットが、交響曲で初めて取り入れられました。
交響曲第6番ヘ長調「田園」 Op.68
作曲時期は第5番とほぼ同じですが、毛色の真逆な交響曲です。この作品には物語があり、小川の流れや鳥のさえずり、嵐など、自然の情景の描写が音楽によってなされています。第2楽章「小川のほとりの情景」、第4楽章「雷・嵐」といったように、各楽章に副題が付けられているのも大きな特徴です。また、楽章を5楽章構成にし、第3~5楽章までは休みなく演奏されることによって、聴き手により“物語”を意識させるなどの工夫が見て取れます。この作品は“標題音楽”として、ベルリオーズやリストなどに大きな影響を与えることとなりました。
交響曲第7番イ長調 Op.92
ワーグナーをして「舞踏の神化」と言わしめた、リズムにスポットを当てた作品です。近年は、人気ドラマ『のだめカンタービレ』の影響で第1楽章ばかりが取り上げられがちですが、世界的には第2楽章が圧倒的に人気でしょう。多くの映画にも使われています。第4楽章はまた、ジェットコースターのような曲で、ノンストップで突き進んでいく様子は圧巻です。
交響曲第8番ヘ長調 Op.93
誰にも献呈されていないことから、よく「ベートーベン自身がもっとも愛した曲」と言われます。ディベルティメント的な作品で、第1楽章こそ壮大に始まりますが、それ以降はスケルツォ的なかわいらしい間奏曲を2つ挟み、軽快な終楽章にいたります。後のプロコフィエフの《古典交響曲》のような、疑似古典性のようなものを感じさせます。
交響曲第9番ニ短調 「合唱付き」Op.125
人類の宝ともいえる、記念碑的作品です。冒頭の空虚5度や第1楽章の大規模に拡大されたソナタ形式、第2楽章のティンパニの活躍、第4楽章冒頭のこれまでの楽章の回想など、革新的な点を挙げるときりがありません。しかし何より特徴的なのは、第4楽章に声楽が入ることでしょう。「シラーの詩『歓喜に寄す』」によって、人類愛を壮大に歌い上げます。
(文・一色萌生)

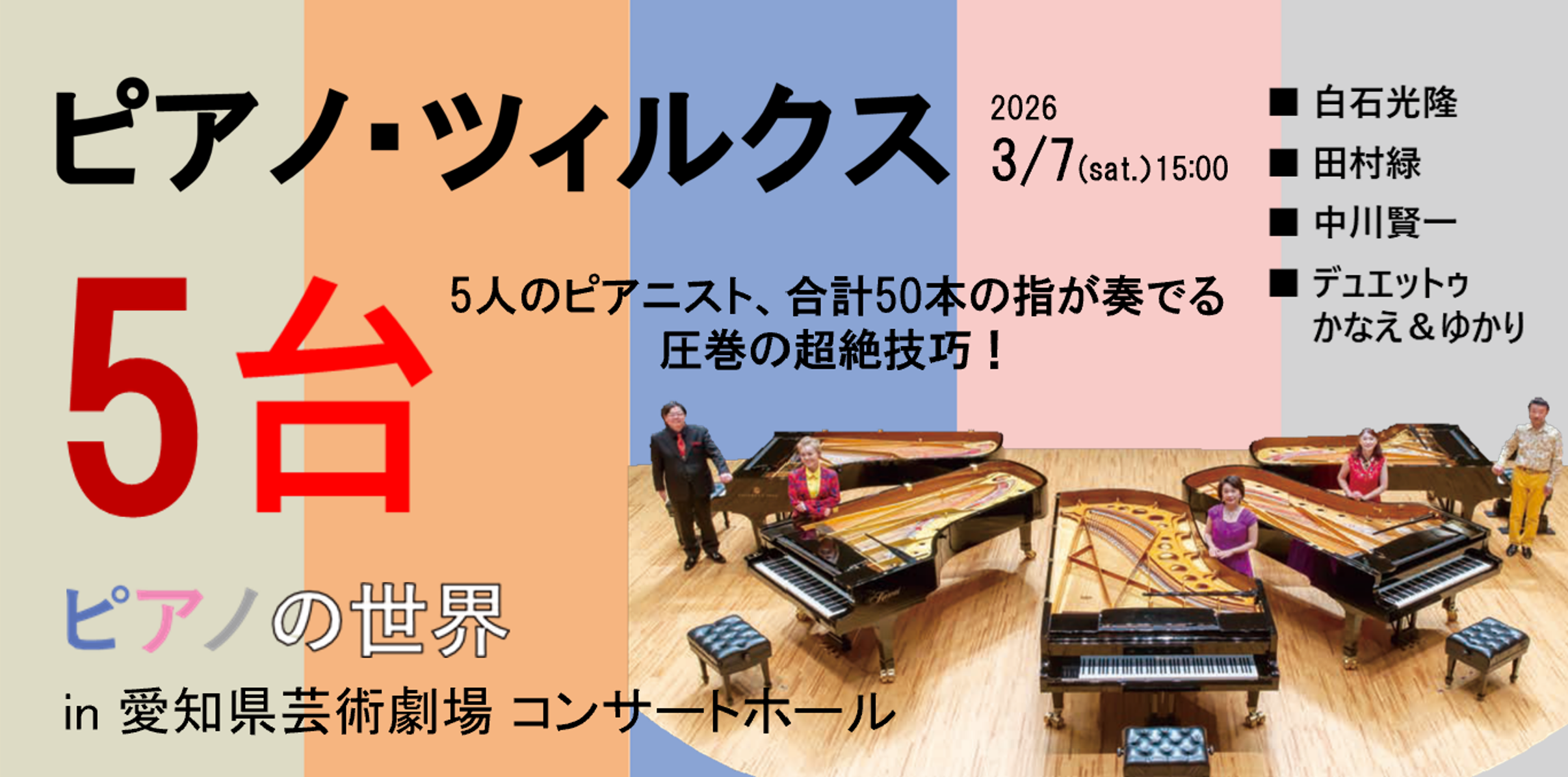




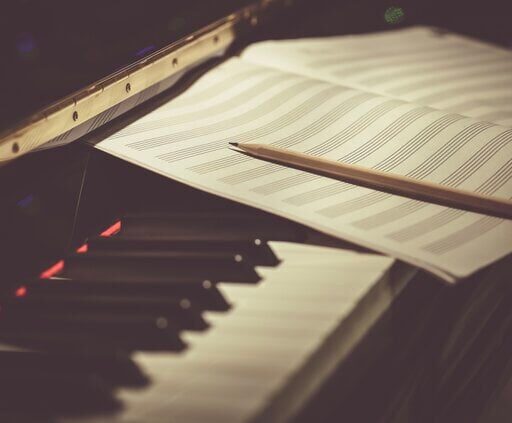
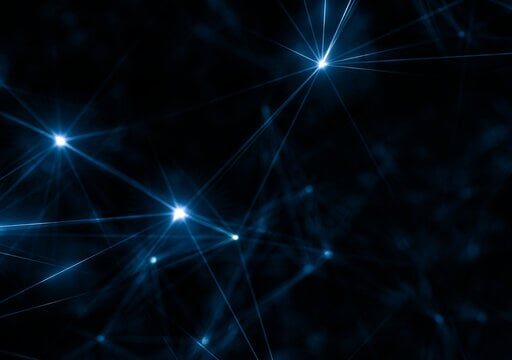








©入り.png)







C福岡諒祠-512x512.jpg)






























