本日は「ショパン・コンサート」。会場は、東京・池袋駅前にある東京芸術劇場のコンサートホール(大ホール)。東京を代表する音楽ホールの一つと見られており、クラシック関係者の間でも、音響が良いということで人気がある。また、大きなホールはピアノに向かないことが多いのだが、当ホールはとても良い。音量、響きの長さとも充分で、しかもクリアに聴こえるのだ。なお席数は1999であり、2000でないのは、ミューズ神のために1席空けてあるからだという。
この「ベスト・リクエスト・クラシック」シリーズは、あるテーマに沿って、事前の投票で選ばれた人気作品ばかりを演奏するというもの。すばらしい。そういうコンサートがあれば良いと思っていた。クラシック演奏会は企画者や演奏家の独りよがりになりがちな分野だ。演奏家だけでなく観客もノれるということは重要なことだ。今回はそのショパン回。司会や出演者自身による解説を交えながら、一流のピアノ奏者たちが演奏する。ピアニストは横山幸雄、高橋多佳子、近藤嘉宏、山本貴志、古海行子。司会はアナウンサー笠井美穂。

ピアノでは、他のどの楽器よりも、体の動きに奏者の音楽感覚が出ているものである。そのため、本日のように、多数のプレイヤーを次々観られる場合には、奏者の動きを比較してみると面白い。今日はそこに注目してみたい。また本日の楽器はカワイのフルコン(Shigeru Kawai)。このあとのリポートでも気にしているが、今日は全体として音に別格的な美しさがある。ピアノが特別なものであることも関係あるだろう。
開演15分前から、ショパンとポーランド音楽の研究者・下田幸二によるプレ・トークが始まった。粛然とライトアップされたステージ。本日の出演陣の多くがショパン国際ピアノ・コンクールのタイトル保持者なので、出場時のエピソードが紹介された。トークが終わって時間を見ると、開演のぴったり5分前。影アナが始まる時刻に合わせてきた。意図したのなら凄い。


司会の笠井による冒頭あいさつの後、【ワルツ 嬰ハ短調(作品64の2)】。演奏者・近藤が黒い細身のスーツで颯爽と登場。いつもながら、ファースト・インプレッションは「スマート」。格好いいなあ。ピアノに座り、すちゃっとメガネをかける。これもいつもの。とても柔らかい音である。打鍵のない時の手が、空中を優雅にふわりと舞う。まるで宮廷楽団の指揮者のようだ。そのまま【ノクターン 変ニ長調(作品27の2)】。抑えめの舞台照明が続く。とても良い雰囲気だ。遂行される誠実な演奏。うっとりする。高音部を細かい音で上行・下行するところは丸くて流れるようだ。近藤ファンはすでに、たまらないだろう。

【ポロネーズ 嬰ヘ短調(作品44)】、演奏は古海。彼女の特性は、粒が丸く、揃っていながら、各音のアタックが明瞭に聞こえること。貴重である。強拍で右肘が下がり、追って左肘も下がる。速いパッセージ中もそうである。小節単位の回転を刻んでいるらしい。堅牢で明晰な演奏である。演奏後トークでは、ショパンの音楽には人類に普遍的な感情が込められているという。そういう演奏だったと思う。

ここでステージが暗転し、ピアノが青く照らし出され、雨音の効果音。このインスタレーションを前に、司会の笠井がショパンの人生の物語を述べる。次に山本による【《24の前奏曲》(作品28)第15番〈雨だれ〉】。体幹をかためて一拍一拍パルスを送り出すような打鍵。集中が深く、透明である。芸劇のパイプオルガンという舞台装置と相まって、宇宙的な時間が流れる。演奏後のトークでは、話し方もしっかり、お辞儀もきっちり。ステージにかける気合いが凄い。


古海の【《12の練習曲》作品10 第5番〈黒鍵〉】。見事なまでに明確な右手が技巧を見せつける。続いて【《12の練習曲》作品25 第1番〈エオリアン・ハープ〉】を披露。本作のタイトルをつけたのはショパン自身ではない(シューマンとされる)が、これは確かに古代風の超然とした響き。真摯な解釈で数千年の歴史空間へ押しやられた。

ここでついに横山と高橋が登場。まずはトーク。横山のフィクサー感が半端ない。しかし高橋は横山と話す時、「部活の1年男子と話す先輩女子」のよう。横山もタジタジだ。そして高橋による【ピアノ協奏曲 第2番(作品21)第2楽章 ピアノ独奏版】。こなれつつも瑞々しい。トークの内容と噛み合った、物語性のある演奏である。

休憩。都立の文化施設の例に漏れず、芸劇コンサートホールもロビーが壮大に広い。美味しいカフェもある。コーヒーを飲みつつプログラムを眺める。そうそう、ホールのベル音は主催者側が結構選べるらしい。そう思って聴いてみると、流れているのはシュルシュルとした不思議な吹鳴系サウンド。曲名「エオリアン・ハープ」に寄せてきている可能性があり、油断ならない。

後半のトークは、司会の笠井と近藤による。ここでは本日の曲目選定の説明など。そして山本の【スケルツォ 第2番(作品31)】。やはり誠実さに満たされた、日本魂あふれる演奏である。パルスにかける瞬間瞬間の圧が凄い。透徹した精神美。またしっかりお辞儀をして退場。

高橋の【《幻想即興曲》(作品66、遺作)】。大御所ピアニストが演奏する難曲。指先が異様に速く手の位置が安定した、音型を大づかみにして転がすような演奏。安心感がある。次に、横山による【《12の練習曲》作品10 第12番〈革命〉】。余裕である。手先や首が小さく弧を描く。鍵盤の上、体の前あたりの空間をターゲットに、音を次々紡ぎ込んでいる感じだ。【バラード 第4番(作品52)】。手慣れた渋さ。配信のアーカイブ映像を観てみると、さらに渋さが際立っている。マイクを通すと普通は平均的な演奏に聴こえるものだが、彼は逆に特別感が増している。


トークののち【バルカローレ(「舟歌」、作品60)】。近藤。右手の速い音型が、モヤにかかったように魔法的。自分がどこにいるのかわからなくなるような没入感がある。彼は今回のアフターイベントとしてサロンコンサートをするという(11月8日夜、カワイ表参道コンサートサロン。昼は高橋と下田による「レクチャーコンサート」)。サロンで聴ける方々がうらやましいと思う。最後は横山による【ポロネーズ 第6番《英雄》(作品53)】。充実的圧倒だ。後半、左手が16分音符の下行を繰り返すところの迫り来る感じは流石である。


横山が他の出演者陣の登場を迎える。最後に一言求められて「んーなんか僕は今日は……」と話す様子には、演奏直後、ハンカチで額を拭きつつにもかかわらず、何の焦りもない。どれだけ慣れているんだろう。

こうしてショパンばかり色々な演奏家で聴いてみると、大御所らしい凄み、中堅の円熟と持ち味、新進的な見どころといった、世代ごとの共通性があることがわかる。しかし真正のファイン・アートの実演の一つ一つには、そのようなカテゴライズで片付けられるものはない。特に今回のように実際にホールで観ると、全ての演奏家が独特の目的に向かって演奏しているのが見てとれる。練習室での彼らの人生、必死の試行錯誤に満たされた日々が目に浮かぶようであり、一人ひとりが貴く愛おしい。
ピアノのみ、特定の作曲家のみであるにかかわらず、広い世界を見た。満足しました。ピンク色のライトアップは芸劇らしい。ファサードを眺めながらスマホに入力、検索ワード「池袋 ポーランド料理」。
(文・秋月洋介 写真・土居政則)

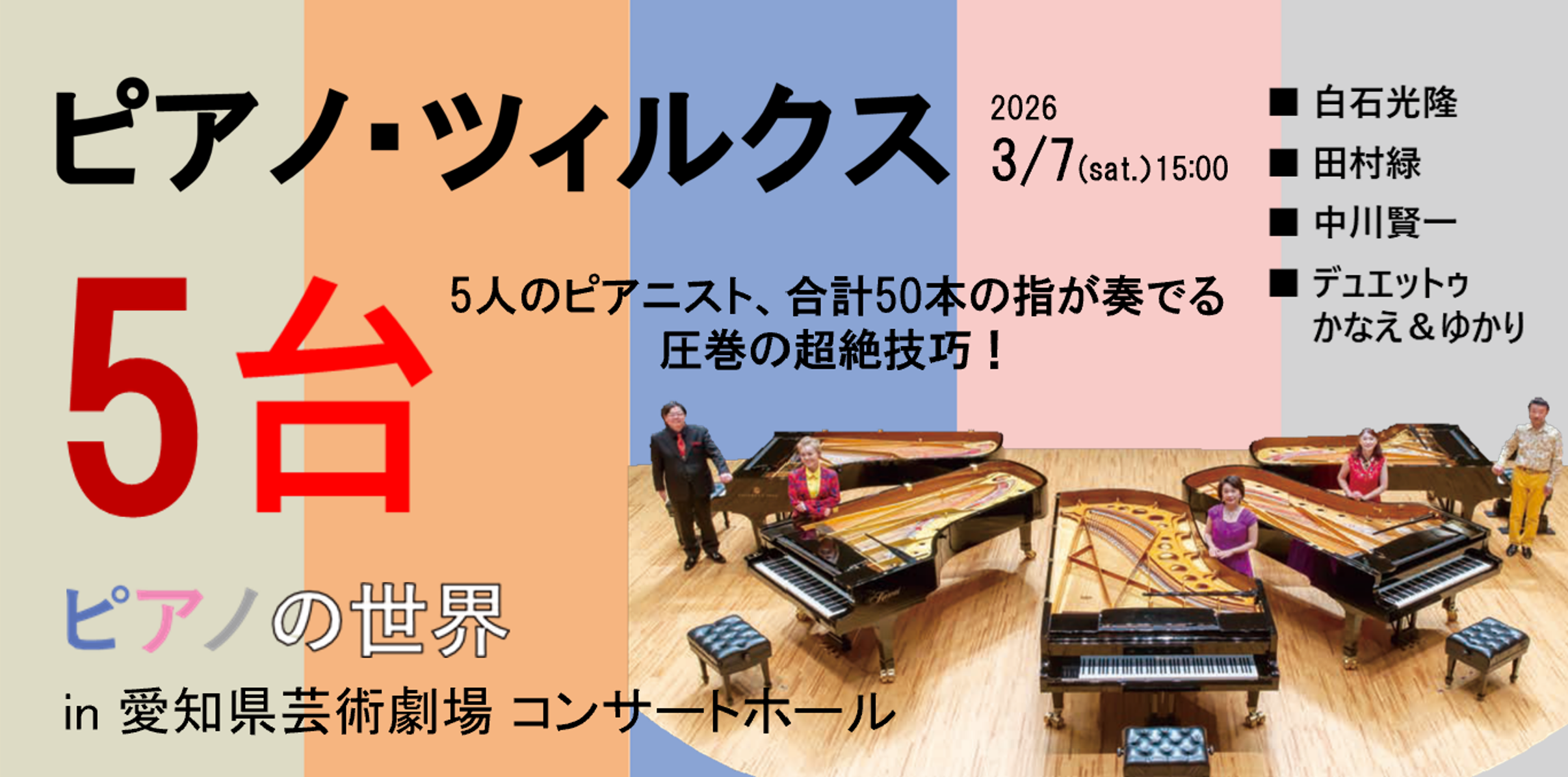














©入り.png)







C福岡諒祠-512x512.jpg)






























