コンサートをより楽しむには、その演奏される曲を理解しておくことが大切である。作品が世に出るまでのエピソードや人気の背景を知れば、コンサートがさらに楽しくなるだろう。そこで始まるのが、コンサートプログラムを簡単に予習する特集企画「Program library」。
今年はセルゲイ・ラフマニノフ(1873-1943)の生誕150周年・没後80年。第1弾として、我々日本人の琴線に触れるメロディを数多く生み出したラフマニノフの魅力に、あらためて迫ってみたい。
ラフマニノフの生きた時代と様式
ラフマニノフの生涯を紐解くことに先立って、彼の生きた時代と音楽の様式というものについて考えてみたい。
ラフマニノフの作品について「ららら♪クラブ」読者の皆さまはどんな印象をお持ちだろうか。甘美で、時にもの悲しい旋律と旋法性を採り入れた和声、楽譜をびっしりと音符で埋めつくす華麗なサウンドなど、「ロマンティック」という印象が強いのではないだろうか。
そして、生誕150年と聞くと「意外と昔の人だな」と感じ、没後80年と聞くと「意外と最近の人だな」と感じることだろう。見方を変えて、我々日本人にとってわかりやすい時代区分でいうと「終戦の2年前」まで生きていた作曲家である。
ラフマニノフは、ちょうど19世紀と20世紀をまたぐ形で激動の時代を生き抜いた。しかし、「時代」の激しさに流されることも、作曲界の「潮流」に飲まれることもなく、その作風はあくまで「個」を貫いている。
1873年にロシア帝国ノヴゴロド州セミョノヴォで生まれたセルゲイ少年は、4歳から音楽の手ほどきを受け、9歳でサンクトペテルブルク音楽院に入学した。12歳の時に「全教科落第」という憂き目を見たが、従兄であるピアニストのアレクサンドル・ジロティの勧めにしたがってモスクワへ移ったあと、厳格なピアノ教師ニコライ・ズヴェーレフのもとで学び、モスクワ音楽院へ転入した。
モスクワ音楽院ではズヴェーレフにピアノを、アントン・アレンスキーに和声を、セルゲイ・タネーエフに対位法を学び、音楽家としての実力をつけていく。また、このころズヴェーレフから紹介されたピョートル・チャイコフスキーに才能を認められている。そして、音楽院の同期には、アレクサンドル・スクリャービンがいた。
特に、ジャンルの幅広さと確たる技術を持った作曲家である、アレンスキーとタネーエフのもとで学んだ経験は、ラフマニノフがほかの「コンポーザー・ピアニスト」とは一線を画して、管弦楽曲の分野でも名作を生み出す下地を作ったと言えるだろう。スクリャービンとともに切磋琢磨したことも、ラフマニノフの音楽家としての成長に大きく寄与した。
一方で、当時のロシア音楽界で一定の存在感を示していた「ロシア五人組」(注釈①)に接近することはなく、また民謡や民族音楽に基づく国民的音楽を志向してのちに「国民楽派」と呼ばれることになる作曲家たちとは異なり、モスクワ音楽院で西欧の音楽理論に基づく堅実な作風を身につけた。
注釈①:「ロシア五人組」は、19世紀後半のロシアで活躍した、ミリイ・バラキレフ(1837 -1910)を中心とする五人組の作曲家グループの通称。バラキレフ、ツェーザリ・キュイ(1835-1918)、《展覧会の絵》などで知られるモデスト・ムソルグスキー(1839-1881)、《イーゴリ公》などで知られるアレクサンドル・ボロディン(1833-1887)、交響組曲《シェヘラザード》などで知られるニコライ・リムスキー=コルサコフ(1844-1908)の5人により結成され、民謡などを重視した民族主義的な作風を追求した。キュイは陸軍軍人、ムソルグスキーは官吏、ボロディンは化学者・医師、リムスキー=コルサコフは海軍軍人と、メンバーの多くが作曲家の他に職業を持っていたことも特徴である。
1891年、ラフマニノフは18歳でモスクワ音楽院ピアノ科を首席で卒業するとともに、ピアニストとしての技術を惜しみなくつぎ込んだ《ピアノ協奏曲第1番 嬰ヘ短調》を完成させ、記念すべき「Op.1」として翌年発表した。
1892年にはモスクワ音楽院作曲科を卒業。同年発表したピアノ曲《幻想的小品集》Op.3は、第2曲〈鐘〉が好評を博し、ラフマニノフにとって最初の成功作となった。
1895年に完成させた《交響曲第1番 ニ短調》Op.13は、1897年にアレクサンドル・グラズノフの指揮によってサンクトペテルブルクで初演されている
「交響曲作曲家」として華々しくデビューする……というラフマニノフの夢は打ち砕かれ、「ロシア五人組」の一角を占める作曲家のツェーザリ・キュイをはじめ、多くの音楽家・評論家にこの作品は酷評された。というのも、当時、ロシアの民族主義的な「ペテルブルク楽派」と国際主義(西欧主義)的な「モスクワ楽派」との対立が深まっていた。「モスクワ楽派」と見なされていたラフマニノフの作品がサンクトペテルブルクで酷評されたことの背景には、ラフマニノフのあずかり知らぬところで発生していた派閥間の対立があったとも考えられる。
この大失敗により、ラフマニノフは神経衰弱を発症し、作曲活動から身を引いて指揮者への転向を考えることになる。ロシア・オペラ界の重鎮である実業家マモントフの「ロシア私設歌劇場」で第2指揮者として活動したほか、ロンドンのフィルハーモニック協会(現:ロイヤル・フィルハーモニック協会、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団の運営母体)の招きで訪英し、指揮者・ピアニストとして共演している。
1901年、ラフマニノフはかの有名な《ピアノ協奏曲第2番 ハ短調》Op.18を完成させて、作曲家としての復活を遂げた。この作品は同年11月に従兄のジロティの指揮、ラフマニノフ本人のピアノで初演され、名実ともに彼の代表作となった。
ラフマニノフというと、やはり「コンポーザー・ピアニスト」のイメージが強い。しかし神経衰弱を発症したことにより、1904年からモスクワのボリショイ劇場の指揮者を2シーズンにわたって務めているなど、純粋な指揮者としての活動も活発に行っていた。
また、オペラ作曲家としても《けちな騎士》《フランチェスカ・ダ・リミニ》を作曲し、1906年に初演している。
ピアニスト、作曲家、指揮者としてロシアで活動して来たラフマニノフは、1906年に家族を連れてドイツのドレスデンへ移住し、1909年まで滞在した。この地で彼は作曲活動に重点を置き、《交響曲第2番》Op.27、《ピアノ・ソナタ第1番》Op.28などを作曲した。
1909年11月には、ニューヨークで《ピアノ協奏曲第3番 ニ短調》Op.30を自らのピアノ演奏、ウォルター・ダムロッシュの指揮、ニューヨーク交響楽団の演奏で初演した。1910年1月にはグスタフ・マーラーとの共演でこの作品を再演している。
ラフマニノフにとって人生最大の転機は、1917年秋の「十月革命」であった。ボリシェヴィキが政権を獲得し、国家体制が大きく変化してゆく中で、ラフマニノフは家族とともにロシアを出国し、ストックホルムとコペンハーゲンへの演奏旅行に出かけた。そして、二度とロシアの地を踏むことは無かった。
1918年にはアメリカに拠点を移し、生計を立てるためにコンサート・ピアニストとして活動。自作がほとんどであったレパートリーを、ベートーヴェンやショパンなどに広げたのもこのころのことである。アメリカではウラディミール・ホロヴィッツらと親交を結び、フリッツ・クライスラーと共演したほか、ピアノ制作者のスタインウェイからは楽器の提供を受けている。
コンサート・ピアニストとしての活躍と反比例するように、作曲活動は一時期下火となっていたが、1926年に久々の作品となる《ピアノ協奏曲第4番 ト短調》Op.40を完成させた。以後《パガニーニの主題による狂詩曲》Op.43(1934年)、《交響曲第3番》Op.44(1936年)などの大規模な作品を次々と手がけた。
このころ、ヨーロッパではすでに「新ウィーン楽派」を発信源とする十二音技法と無調音楽が広がりを見せており、《交響曲第3番》と同時期に、十二音技法で有名なアルバン・ベルクが《ヴァイオリン協奏曲》を完成させていたが、ラフマニノフはあくまで調性と旋法に基づくロマンティックな作風を貫いた。
1942年にカリフォルニアへ転居して以降、体調がすぐれない中でも演奏会をキャンセルすることなくピアニストとして走り続けてきたが、1943年3月28日、70歳の誕生日を目前にしながらビバリーヒルズの自宅で死去した。
ラフマニノフのピアノ独奏曲・ピアノ協奏曲紹介
ラフマニノフのピアノ曲としてまず初めに紹介したいのは、1892年に完成させた《幻想的小品集》Op.3だ。もの悲しい旋律が切々と歌われる第1曲〈エレジー〉、左手がチェロかバリトン歌手のように歌う第3曲〈メロディ〉、軽妙洒脱な第4曲〈道化役者〉、そしてワルツ風の第5曲〈セレナード〉と佳曲が並ぶが、なんといっても代表的なのは第2曲〈前奏曲〉だろう。〈鐘〉の愛称でも知られるこの作品は、オーケストラに匹敵する重厚なサウンドで、ラフマニノフのピアノ書法の傾向をはっきりと示している。
1901年から1903年にかけて書かれた《10の前奏曲》Op.23と、1910年に完成させた《13の前奏曲》Op.32は、どちらもラフマニノフの作品を、そしてピアノ独奏曲としての「前奏曲」を語る上で外せない作品だろう。《10の前奏曲》の第2曲の華やかさや、第5曲〈ア・ラ・マルチア〉の特徴的なリズム・パターン、《13の前奏曲》の第12曲の冒頭から幾度も現れる、冷たい風が吹き抜けてゆくようなパッセージなど、多種多様な魅力を持った作品である。
1910年に書かれたOp.33、1917年ごろに書かれ1920年に出版されたOp.39のふたつからなる練習曲《音の絵》は、Op.33の第2曲の色彩豊かな転調や、「赤ずきんちゃんとオオカミ」の愛称でも知られるOp.39の第6曲での音による描写など、音による「画家」としての才能を惜しみなく発揮している。
いまや多くのピアニストが主要なレパートリーとしている《ピアノ・ソナタ第2番 変ロ短調》Op.36は、1913年に完成され1931年に改訂されたものの、ラフマニノフ本人の生前は高い評価を得られず、しかもウラディミール・ホロヴィッツによるふたつの稿を折衷した編曲版のほうが知られている状態であった。この作品がラフマニノフのピアノ独奏曲における重要な地位を獲得したのは、1973年の「生誕100周年」のころである。
ピアノ協奏曲紹介
ここからはピアノ協奏曲に焦点を当ててみたい。
1891年に完成させた《ピアノ協奏曲第1番 嬰ヘ短調》Op.1は、作品番号も示す通りラフマニノフにとっての「デビュー曲」ともいうべきもの。ピアノの超絶技巧に重きを置きつつも、オーケストラもよく書き込まれており、若きラフマニノフの才能が爆発している。
《ピアノ協奏曲第2番 ハ短調》Op.18は、いわずと知れた名曲。ピアノが分厚い和音を奏でながら音量を増していく冒頭部分は、身長198センチ、そして13度音程(30センチ)を楽につかめたといわれるラフマニノフの身体と手の大きさを今に伝えている。
《ピアノ協奏曲第3番 ニ短調》Op.30は、第2番と双璧を成す人気の作品。第2楽章の美しさと和声の切なさはラフマニノフの作品中屈指のものであろう。第3楽章の高揚感は第2番をも上回っている。
1934年に完成した《パガニーニの主題による狂詩曲》は、ラフマニノフの作曲技法の粋を集めた作品。とりわけ第18変奏が有名であるが、実は主題の旋律を裏返すという、作曲技法上の高度なテクニックが用いられている。
1926年に完成し、1941年に決定稿が仕上げられた《ピアノ協奏曲第4番 ト短調》Op.40は、《パガニーニの主題による狂詩曲》とともに、ロシアを去ってからのラフマニノフが手掛けた、数少ない作品のひとつだ。ラフマニノフのほかの作品に比べると演奏機会になかなか恵まれない作品であるが、雄大なスケール感と優美さとを兼ね備えている点において、ラフマニノフらしさに満ちている。アメリカに拠点を移して以降の作品ということもあり、ピアノとオーケストラの絡ませ方にジャズの影響が見受けられる。
それまでのラフマニノフのピアノとオーケストラのための作品は、ひとことで言えば「シンフォニック」だが、この作品では、トランペットをはじめ、管楽器とピアノが緻密なアンサンブルを繰り広げる場面が目立ち、「室内楽的」な傾向を見せている。第1楽章のコーダ部分では、リズムの面ではっきりとスウィング・ジャズが現れている。第3楽章のクライマックス部分は、和音とリズムの両面において、1924年に発表されたガーシュウィンの《ラプソディ・イン・ブルー》のような、「シンフォニック・ジャズ」の香りを放っている。
ラフマニノフのピアノ独奏曲、そしてピアノとオーケストラのための作品について紹介して来たが、「後編」では、ラフマニノフの作曲家としての「幅の広さ」に焦点を当て、管弦楽曲をはじめとする他のジャンルの作品について掘り下げていく。
自身が活発に演奏活動を展開していたこともあり、「コンポーザー・ピアニスト」としてのイメージが強いラフマニノフだが、その創作活動は決して「ピアノありき」のものではなかったことを、メモリアル・イヤーの今こそあらためてご紹介したい。
<文・加藤新平>



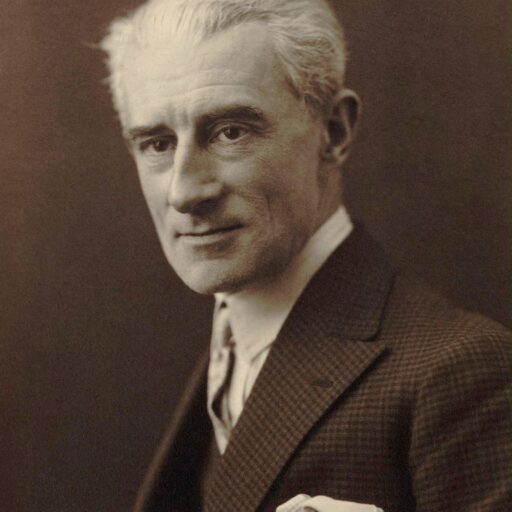

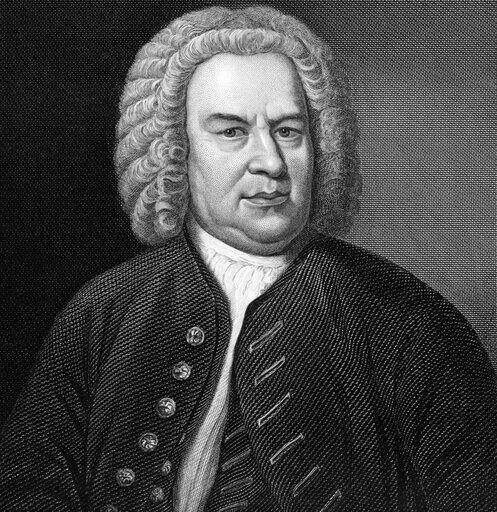







©入り.png)






C福岡諒祠-512x512.jpg)






























