コンサートをより楽しむには、その演奏される曲を理解しておくことが大切である。作品が世に出るまでのエピソードや人気の背景を知れば、コンサートがさらに楽しくなるだろう。そこで始まるのが、コンサートプログラムを簡単に予習する特集企画「Program library」。
Vol.3は、音楽史において極めて重要な作曲家のひとりであり、日本では「楽聖」とも呼ばれるベートーヴェン。「交響曲編」「ピアノ・ソナタ、ピアノ協奏曲編」「室内楽曲、管弦楽曲、声楽曲編」に分けて、その生涯や、コンサートのプログラムに選ばれることの多い作品を簡単にご紹介しよう
「交響曲編」ではベートーヴェンの生涯と交響曲を、そして「ピアノ・ソナタ、ピアノ協奏曲編」と続き、本稿ではベートーヴェンの室内楽曲、管弦楽曲、声楽曲について「筆者の推し曲」に絞ってご紹介したのち、「聴き方・聴きどころ」を紐解いていく。
ベートーヴェンの室内楽曲紹介
まずはヴァイオリン・ソナタから、第5番 ヘ長調 Op.24をピックアップ。「春」の愛称で親しまれるこの作品は、冒頭からその明るさと華やかさで聴く者の耳をつかんで離さない。単に旋律が美しいだけでなく、ピアノが伴奏に甘んじることなしにヴァイオリンと対等の立場で歌いかわすあたりも、この作品の魅力だ。もっとも、ベートーヴェン以前のヴァイオリン・ソナタの多くは「ヴァイオリンつきのピアノ・ソナタ」であった……ということに留意する必要があるだろう。
ベートーヴェンは、番号無しの作品も含めて10曲のヴァイオリン・ソナタを1803年までに書き上げた。第9番 イ長調はヴァイオリニストのロドルフ・クロイツェルに捧げられ、「クロイツェル・ソナタ」の愛称で親しまれる。ベートーヴェン自身はこの作品に「協奏曲のように競って演奏されるヴァイオリン助奏つきのピアノ・ソナタ」という趣旨の副題をつけており、ヴァイオリン・ソナタでありながらピアノに極めて重きが置かれている。第1楽章はイ長調で重厚に開始されるが間もなくイ短調の陰が忍び寄り、アレグロ部分はイ短調で駆け抜けていく。第2楽章は優美な変奏曲。第3楽章は快活な「タランテラ」のリズムが特徴的な、ラテン的な明るさに満ちている。この作品に触発されて書かれたのが、レフ・トルストイによる小説『クロイツェル・ソナタ』であり、さらにこの小説に刺激を受けて書かれたのがヤナーチェクの弦楽四重奏曲第1番《クロイツェル・ソナタ》である。ベートーヴェンとヤナーチェクが、ロシアの文豪を介してつながっているのである。
「クロイツェル・ソナタ」から9年の時を経て、1812年にベートーヴェンが書いた最後のヴァイオリン・ソナタが、第10番 ト長調 Op.96だ。4つの楽章それぞれに「歌心」があり、第4楽章の変奏曲などベートーヴェンらしい技術が盛り込まれる一方で、第1楽章の透明感はブラームスを、第3楽章スケルツォの焦燥感はシューマンを想起させる。
ベートーヴェンは学生時代に劇場のオーケストラでヴィオラを弾き、またピアノの名手でもあったが、チェロに関しては特段の演奏経験を持たなかった。しかし、勝れた腕前のチェリストの友人に恵まれ、6曲のチェロ・ソナタを残している。
本稿では6曲の中から、第3番 イ長調 Op.69をご紹介する。チェロの独奏でのびやかにメロディが歌われる冒頭部分から、チェロという楽器の特性がフルに活かされている。とりわけ、これ以前の作品ではあまり顧みられてこなかった、チェロの高音域に光が当てられていることは注目に値する。
ベートーヴェンの手がけた器楽曲のジャンルの中で、ピアノ・ソナタに次いで曲数が多いのは弦楽四重奏曲である。番号付きの作品だけで16曲が書かれている。
初期の作品から、第6番 変ロ長調 Op.18-6をまずご紹介したい。明るくわかりやすい旋律と、旋律と伴奏の役割分担がはっきりした書法は、いかにも「古典的」だが、それゆえに親しみやすい。第3楽章スケルツォの、思わずつんのめってしまうようなシンコペーションも印象的。
1806年、アンドレイ・ラズモフスキー伯爵の依頼で作曲された3曲は「ラズモフスキー四重奏曲」と呼ばれている。「ラズモフスキー第1番」こと、第7番 ヘ長調 Op.59-1は、中期の弦楽四重奏曲の代表作とも言われている。第1楽章冒頭、チェロによって主題が提示された瞬間から、この作品が「意欲作」であることを印象付ける。第4楽章ではロシア民謡が用いられており、民謡編曲の分野でも優れた業績を残したベートーヴェンならではの作品となっている。そして、なんといってもこの曲の特徴は、4つの楽章すべてがソナタ形式で書かれていることであろう。交響曲に匹敵するどころか、ある部分では交響曲を凌駕するほどの充実度をもつ作品だ。
後期の作品から、第15番 イ短調 Op.132を推したい。この作品は1825年に書かれたもので、五楽章構成である。第1楽章冒頭から、4つの楽器が次第に重なり幻想的な雰囲気を作り出す。第2楽章は「スケルツォ」というジャンルの確立者ともいうべきベートーヴェンにはめずらしく、メヌエット風。そしてこの曲の中心を成しているのは第3楽章。「病より癒えたる者の神への聖なる感謝の歌」という副題が添えられたこの楽章は、ヘ長調……ではなく、ヘ音を終止音とするリディア旋法(ヘ長調の音階の4番目の音を、半音上げたものに相当)で書かれた、明るく透明感のあるコラールである。短い行進曲風の第4楽章から続けて奏される第5楽章の主題は、当初「合唱無し」で構想されていた交響曲第9番の、第4楽章の主題を転用したものと伝えられている。
ベートーヴェンにとって事実上最後の「まとまった規模の作品」となった第16番 ヘ長調 Op.135は、古典的な四楽章形式に回帰しているが、その内容はやはり新しい。第1楽章では冒頭からヘ長調とは異なる響きが現れ、第2楽章はスケルツォだが「旋律と伴奏」という役割分担ではなく、4つの楽器が少しずつずれながら演奏することでリズムが生まれる、いわば「弦楽四重奏でしかできない書法」が採られている。第3楽章の美しさは特筆に値し、ブラームス、ブルックナー、マーラーなど、後世の作曲家たちへと通じる要素が見られる。そして、第4楽章の冒頭では、序奏の主題に「そうでなければならないか?」という問いかけが、主部の明るい主題に「そうでなければならない!」という回答が書かれている。このふたつの主題は、のちのセザール・フランクの傑作《交響曲ニ短調》に多大なる影響を与えた。
管弦楽曲・協奏曲紹介
ベートーヴェンは、交響曲のほかにも、バレエ音楽、劇音楽など、さまざまな管弦楽曲を手がけた。
ベートーヴェンにとって、初期の大ヒット作となったのが、バレエ音楽《プロメテウスの創造物》Op.43である。1801年に初演されたこの作品は、現在では序曲しか演奏されないが、冒頭の転調の連鎖で意表を突き、ゆったりとした歌謡的な旋律を聴かせたのち、息つく暇もないほどの超高速のアレグロで走り去る、ベートーヴェンのエネルギーが炸裂している1曲である。
1806年に書かれたヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61は、メンデルスゾーン、ブラームスの作品と並ぶ人気曲。第1楽章の冒頭からティンパニが活躍するあたりはベートーヴェンならでは。筆者は第3楽章のエネルギッシュなロンドを推したい。
序曲《コリオラン》Op.62は、1807年に完成した演奏会用序曲(特定のオペラなどのためではなく、単体の楽曲)であり、ハインリヒ・ヨーゼフ・フォン・コリンの戯曲『コリオラン』を観劇したときの衝撃を曲にしたものといわれている。ローマ帝国で権勢をふるったが政治上の意見の違いで国を追われたコリオラヌスが、隣国の将軍となってローマに攻め入るものの、妻と母の忠告によって再びローマ帝国に寝返ったために命を落としてしまう、という悲劇を、オーケストラのみで描き切っており、10分に満たない作品ながら、2時間半のオペラに匹敵するほど劇的である。
ベートーヴェンにとって最後の「オーケストラのみの作品」となった《献堂式》序曲 Op.124は、1822年に祝典劇『献堂式』のための劇音楽として作曲された。実は交響曲第9番が1824年に初演された際にも、同じ演奏会で演奏された作品でもある。和音の打撃による堂々たる開始と、それに続く讃歌風の旋律、そして金管楽器のファンファーレの背後で駆け回るファゴットと、ベートーヴェンの作曲スキルの粋を集めたような展開が続くが、盛り上がっていった頂点で現れる、アレグロ部分の主題はなんと対位法を駆使した「二重フーガ」という、さらに高等なテクニックが用いられている。交響曲第9番にもその成果が表れているが、このころのベートーヴェンはルネサンスやバロックの音楽を研究しており、とりわけJ.S.バッハやヘンデルの作品に親しんでいた。この《献堂式》序曲は、ベートーヴェンによるバロック音楽研究がみごとに結実したものであると言えよう。
ベートーヴェンのその他の楽曲紹介
紙幅の都合上、楽曲数をしぼってのご案内となるが、ベートーヴェンの作品のうち、ここまでの枠組みに収まらないものをまとめてご紹介する。
ピアノ、合唱、オーケストラのための《合唱幻想曲》Op.80は、1808年に作曲された作品であるが、演奏機会に恵まれなかった。しかし近年再評価の機運が高まっている。交響曲第5番と同時期に書かれた作品であるが、合唱と管弦楽の融合や、その旋律の一部に交響曲第9番の萌芽がみられる。
1816年に作曲された連作歌曲集《遥かなる恋人に寄す》Op.98は、6曲からなる歌曲集である。ベートーヴェンが大スランプにおちいっていたころの作品だが、スランプを感じさせぬ充実した内容をもち、第1曲の主題を第6曲で回帰させるなど構成面でも工夫がみられる。シューマンがこの曲をとても好み、《幻想曲ハ長調》などに引用していることでも知られている。
1823年に完成した《ミサ・ソレムニス》Op.123は、5年がかりで作曲された、ベートーヴェンにとって最後の大規模な宗教曲である。テクストはラテン語のミサの典礼文であるが、その扱い方が独特であることから、教会ではなくコンサート向きの作品だと評する向きも多い。特に〈グローリア〉の高揚感は、同時期に作曲された交響曲第9番にも匹敵する。対位法が駆使されていることも、《献堂式》序曲と同様、ベートーヴェンのバロック音楽研究の賜物であろう。
ベートーヴェンの聴き方・聴きどころ
ベートーヴェンの聴き方・聴きどころとしては、まずピアノ曲における「低音域の和音」に注目してほしい。
ピアノの低音域で、「ドミソ」のように三和音を鳴らすことは、楽器の特性上響きが硬くなりやすいこともあり、ベートーヴェン以前の作曲家はあまり行っていなかった。しかし、ベートーヴェンはピアノ・ソナタ第1番 ヘ短調から、この「低音域の和音」を好んで使用し、ピアノの「打楽器」的な側面を強調している。
また、ピアノ・ソナタ紹介でも言及したが、ピアノという楽器の性能を最大限引き出し、1台の楽器からオーケストラに匹敵する充実したサウンドを生み出していることも、ベートーヴェンの特徴と言えるだろう。
「短いモチーフを積み重ねて音楽を構成する」(動機労作)という技法も、ベートーヴェンが得意としたもののひとつだ。代表的なのが「運命」こと交響曲第5番だが、あの「ン、ダダダーン」を徹底的に散りばめてひとつの作品を作り上げるその手腕はただものではない。
ひとつの旋律を「主題」とし、その旋律を変奏しながら規模の大きい楽曲に仕立て上げる「変奏曲」でもベートーヴェンは数多くの傑作を残した。「あ、変奏ってここまでやっちゃっていいんだ」と、後世の作曲家に勇気を与えてくれた存在でもある。
「楽聖」というイメージと、渋い表情の肖像画などから「お堅いマジメ君」の印象をお持ちの方もいるだろうが、ベートーヴェンは実はジョーク好きで、音楽の面でも「聴き手を楽しませる」を通り越して「聴き手を笑わせる」ことに重きを置いているケースがある。交響曲第8番の第2楽章などがその最たる例だ。
ベートーヴェンは「ソナタ形式」というものを徹底的に追求し、ふたつの主題が対立し、対話していった先にあるものを描き出すことに力を入れた。ソナタ形式のもつ「回帰のカタルシス」というものを強めた彼の作品は、聴き手に強い満足感と達成感を与えてくれる。
まとめ
このように、ベートーヴェンの「聴き方・聴きどころ」はさまざまだが、本稿を締めくくるにあたり「ららら♪クラブ」読者の皆さまにどうしてもお伝えしたいことがある。
ベートーヴェン好きを自負する方も、そうでない方も、ぜひ、ベートーヴェンのさまざまなジャンルの作品を聴いてほしい。ピアノ曲だけで、オーケストラ曲だけで、弦楽四重奏曲だけでベートーヴェンを「知る」ことの、なんともったいないことか。横断的に、かつ網羅的に彼の作品を聴くからこそ、見えてくるものがあるはずだ。
<文・加藤新平>





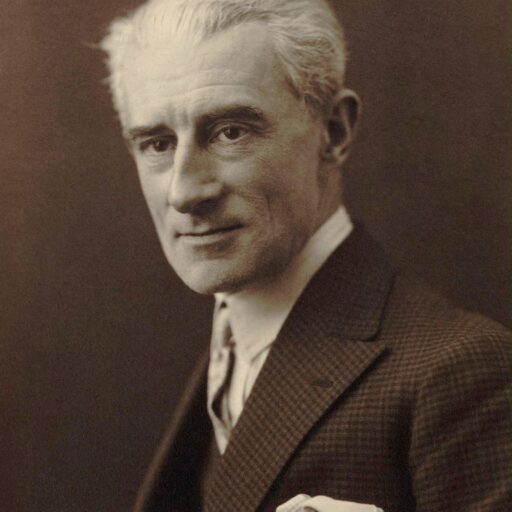

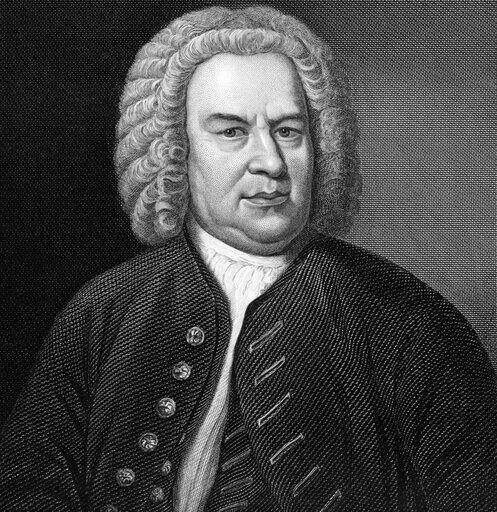






©入り.png)






C福岡諒祠-512x512.jpg)






























