コンサートをより楽しむには、その演奏される曲を理解しておくことが大切である。作品が世に出るまでのエピソードや人気の背景を知れば、コンサートがさらに楽しくなるだろう。そこで始まるのが、コンサートプログラムを簡単に予習する特集企画「Program library」。
Vol.3は、音楽史において極めて重要な作曲家のひとりであり、日本では「楽聖」とも呼ばれるベートーヴェン。「交響曲編」「ピアノ・ソナタ、ピアノ協奏曲編」「室内楽曲、管弦楽曲、声楽曲編」に分けて、その生涯や、コンサートのプログラムに選ばれることの多い作品を簡単にご紹介しよう
「交響曲編」では、ベートーヴェンの生涯と彼の交響曲についてご紹介した。本稿ではピアノ・ソナタ、そしてピアノ協奏曲に焦点を当てる。なお、紙幅の都合上、ピアノ・ソナタについては「筆者の推し曲」に絞らせていただくことをご容赦願いたい。
ベートーヴェンのピアノ・ソナタ紹介
ベートーヴェンのピアノ・ソナタは、番号付きの作品が32曲、番号無しの作品が5曲あり、彼の創作活動の中核を成している。
ベートーヴェンにとって、初めて出版されたピアノ・ソナタである第1番 ヘ短調 Op.2-1は、ヘ短調という調性の選択を含めて「悲劇性」を打ち出しているほか、フォルテとピアノ、厚い響きと薄い響きの強烈な対比によって、ベートーヴェンのピアノ・ソナタの特徴である「オーケストラ的」な方向性を示している。
こうした方向性をさらに推し進めた作品が、第4番 変ホ長調 Op.7であろう。第1楽章冒頭の全合奏によるファンファーレや、弦楽器と木管楽器によるカンタービレな旋律など、オーケストラを想起させるサウンドと、第4楽章における、ピアノという楽器の音域の広さを活かした音楽とが好対照を成している。
我々にとってもっとも馴染み深い作品のひとつが、「悲愴」の愛称で知られる第8番 ハ短調 Op.13だ。第1楽章の重厚な序奏と疾走感のあるアレグロは、まさに交響曲を思わせる。実際、この楽章は作曲を学ぶ学生にとって「オーケストレーション」の課題曲となることも多く、著名な例ではアントン・ブルックナーによるものが知られている。第2楽章はその旋律の美しさからさまざまに編曲され、日本ではとりわけボートレースのCMソング《見えないスタート》でよく知られている。そして「悲愴」のタイトルにふさわしい焦燥感たっぷりの第3楽章は、韓国ドラマ『ベートーベン・ウイルス』のオープニング曲にもなっている。
第14番 嬰ハ短調 Op.27-2は「月光」という愛称が独り歩きし、まるで描写音楽かのように扱われているが、実際には、通常なら速いテンポの楽章で始まるはずのピアノ・ソナタをあえてゆっくりとしたテンポの楽章で始めるなど、革新性に満ちた作品である。
第15番 ニ長調 Op.28は、もうひとつの「田園」だ。第1楽章では、まるでティンパニのように低音域で同音が連打される中、穏やかに主題が提示される。この「持続する低音」は第4楽章にもあらわれ、作品の持つ牧歌性に一役買っている。
第17番 ニ短調 Op.31-2は、長年「テンペスト」の愛称で親しまれてきた。これは、ベートーヴェンの弟子シンドラーがこの曲の解釈について尋ねた際に「シェイクスピアの『テンペスト』を読みなさい」とベートーヴェンが答えた……という逸話に由来するが、現在ではこの逸話はシンドラーの捏造であったとされている。したがって本稿では、この作品をシェイクスピアと結びつけることは一切しない。こうした逸話に流されることなく、音そのものに向き合うと、オペラの「レチタティーヴォ」を取り入れるなど、1台のピアノでどこまで劇的な表現が可能かをベートーヴェンが追究していた様子が聴きとれる。
交響曲編でも述べたとおり、ベートーヴェンはその生涯にわたってよき支援者(パトロン)に恵まれた。第21番 ハ長調 Op.53は、ボン時代からの支援者ヴァルトシュタイン伯爵に捧げられている。弦楽器による第1主題と、管楽器による第2主題……と言いたくなるほど、第1楽章は交響曲的な性格が強い。第2楽章の転調の巧みさはベートーヴェンならでは。そして耳には比較的穏やかながら、左右の手が交差するなどそれなりに高度なテクニックが求められる第3楽章。特に終盤の内声のトリルは見かけ以上に至難の技だ。
「熱情」の愛称を持つ第23番 ヘ短調 Op.57も、「悲愴」と並んで人気の高い作品だ。オクターヴユニゾンで朗々と奏でられる旋律や、第1楽章に散りばめられた、交響曲第5番を想起させる「運命の動機」など、さまざまな特徴がある作品だが、左右の手が互い違いに組み合わせられてひとつの音楽が成り立つように工夫された箇所が多く、オーケストラ的な傾向が強いベートーヴェンのピアノ・ソナタの中で、あえて「ピアノでしかできないこと」を追究した作品のように思われる。
第26番 変ホ長調 Op.81aは、第1楽章に〈告別〉、第2楽章に〈不在〉、第3楽章に〈再会〉の副題がつけられている。第1楽章は交響曲を想起させる重厚さ、第2楽章はハ短調でありながらなかなか調が定まらない浮遊感、そして第3楽章はピアノ協奏曲を思わせる華やかさが特徴である。
ベートーヴェンのピアノ・ソナタの中で唯一「ホ短調」で書かれており、師匠ハイドンが好んだ二楽章形式のソナタへ回帰する方向を見せている点で異彩を放っているのが、第27番 ホ短調 Op.90である。日本の音楽評論家、山根銀二の著作によると、第1楽章は「頭と心臓の闘い」、第2楽章は「恋人との対話」と書くべきものとベートーヴェンはシンドラーに語っており、この作品の献呈者であるリヒノフスキー伯爵の恋愛を描いたものとされている。……が、そういったバックストーリーを抜きにして、第1楽章の力強さと第2楽章の愛らしさの対比がみごとな作品である。
第28番 イ長調 Op.101は、第1楽章が穏やかで歌謡的という点で、ベートーヴェンのほかのソナタとは一線を画している。第2楽章の行進曲は、付点リズムの多用や転調の仕方に、シューマンの作品を予感させる要素がある。第3楽章は陰鬱で長い序奏の果てに、力強い主題が表れるフィナーレ。対位法を駆使して盛り上げてゆく手法はベートーヴェンならでは。
「ハンマークラヴィーア」の愛称で知られる第29番 変ロ長調 Op.106は、ベートーヴェンのピアノ・ソナタの中でも最大の規模を誇る作品である。オーケストラの全合奏を思わせる冒頭と、弦楽器と木管楽器を想起させる経過句など、第1楽章は特に交響曲的な傾向が強い。第2楽章は優美なスケルツォ、第3楽章は重々しい緩徐楽章である。そして第4楽章は「レチタティーヴォ」と「フーガ」という、ピアノ・ソナタとしてはかなり異例の構成を持つ。特にフーガ部分は主題の音数が非常に多く、演奏至難な作品だ。なお、オーストリアの指揮者フェリックス・ワインガルトナーによるオーケストラ編曲版が存在し、「もしもベートーヴェンのピアノ・ソナタをオーケストラで演奏したらどうなるか」という問いの答えとなっている。
第30番 ホ長調 Op.109は、筆者が個人的に推したい作品だ。まるでベートーヴェンによる即興演奏をそのまま楽譜に書き留めたかのように、ソナタ形式でありながら第1主題と第2主題のテンポも拍子もまったく異なる第1楽章、同じくソナタ形式でありながら、その推進力の強さとふたつの主題の類似性から楽曲全体をひとつの色で染め上げている第2楽章、そしてベートーヴェンの作曲技術の粋を集めた変奏曲である第3楽章、どれをとっても一級品の作品である。
第31番 変イ長調 Op.110は、優しい歌心に満ちた第1楽章、当時の流行歌を取り入れたと言われているスケルツォ風の第2楽章、「レチタティーヴォ」「嘆きの歌」など、さまざまな「うた」が現れる第3楽章、いずれも独特な構成を持つ。「ピアノ1台による歌曲集」ともいうべき作品。
ベートーヴェンにとって最後のピアノ・ソナタとなった第32番 ハ短調 Op.111は、不協和音と付点リズムが印象的な序奏に始まり、対位法を駆使しながらも悲劇性の極めて強い第1楽章と、透明感に満ちたハ長調の主題をもとに紡がれる変奏曲である第2楽章とが好対照を成している。ベートーヴェンが長い旅路の果てにたどり着いた「頂点」とも言うべき作品である。
ベートーヴェンのピアノ協奏曲紹介
ベートーヴェンとピアノを語る上で、もうひとつ、忘れてはならないのがピアノ協奏曲だ。
1784年、ルートヴィヒ少年が13歳のときに作曲したピアノ協奏曲 変ホ長調 WoO.4は、ピアノパートの草稿のみが現存しており、オーケストラの部分はさまざまな補筆完成版がある。若き日のベートーヴェンを知る意味で重要な作品であろう。
出版順の関係で「第2番」となり、作品番号も繰り下がっているが、1786年から1795年にかけて作曲され、ベートーヴェンのウィーン・デビューを飾る作品となったのが、ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 Op.19である。オーケストラの編成はフルート1,オーボエ2,ファゴット2、ホルン1、弦楽五部と小さく、ハイドンやモーツァルトの影響も濃いとされている本作だが、付点リズムと不協和音を効果的に用いている第1楽章は紛れもなく「ベートーヴェンらしさ」全開である。装飾性に富んだ第2楽章、舞曲風の第3楽章も、随所にベートーヴェンならではの響きが聴かれる。
交響曲第1番の発表に先駆けて作曲されたのが、1795年に発表されたピアノ協奏曲第1番 ハ長調 Op.15である。オーケストラの編成も交響曲に匹敵するものとなっている。堂々として長大で、しかも当時はピアニストが即興的に演奏することの多かったカデンツァまでベートーヴェン自身が作曲している第1楽章、オペラ・アリアを想起させる歌謡性に富んだ第2楽章、快活で楽しい第3楽章、いずれもウィーンで勢いに乗る「コンポーザー・ピアニスト」の自信作を印象付ける。
ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 Op.37は、ベートーヴェンのピアノ協奏曲の中で唯一短調の作品である。ベートーヴェンの書く「ハ短調」と言えば……お察しの通り悲劇性が強い。この時代のピアノ協奏曲の第1楽章は、「オーケストラによる第1提示部」と「ピアノ独奏+オーケストラによる第2提示部」がそれぞれある、「協奏ソナタ形式」を採っているが、第1楽章の冒頭、第1提示部は、予備知識ゼロで聴いたら交響曲と聞き間違うほどの充実感を持っている。第2楽章は緩徐楽章だが、ハ短調の第1楽章に対して「遠隔調」、すなわち関係性の薄い調であるホ長調で書かれているほか、オーケストラを伴わないピアノ独奏で開始されるなど、独特の構成を持っている。第3楽章はベートーヴェンらしい推進力に満ちたロンド楽章。短いカデンツァを挟んでハ長調へ転調し、元気よく一気に駆け抜けるあたり、モーツァルトのピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K.466を模したものとも、あるいはベートーヴェン自身が交響曲第5番、通称「運命」で示したような「苦難を経て勝利へ」という構図を示したものとも考えられる。
ピアノ協奏曲第4番 ト長調 Op.58は、第1楽章冒頭が静かなピアノ独奏で開始されるという点で、当時としては斬新な作品であった。楽章全体にわたってベートーヴェンの転調の技術が遺憾なく発揮されているほか、第2提示部がすでに展開部の様相を呈するなど、かなり斬新な印象を受ける。第2楽章は力強く奏される弦楽合奏と、静かに切々と歌うピアノとの対話。まるでオペラのワンシーンを思わせる。そして第3楽章のロンドは、ハ長調からト長調への転調が劇的であり、リズムで畳み掛けるさまは《交響曲第7番》にも通じるものがある。
ベートーヴェンにとって事実上最後のピアノ協奏曲となった、ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 Op.73は、「皇帝」の愛称で知られる。第4番以上に型破りな作品であり、第1楽章の冒頭ではピアノによるカデンツァが奏される。第1提示部におけるオーケストラの充実ぶりは第3番をも凌駕しているほか、ピアノパートの華麗さも際立っている。なお、協奏曲の第1楽章においては、終結部の直前にピアノ独奏のカデンツァが置かれることが通例であるが、この作品に関してはベートーヴェン自身が「カデンツァは不要」と書いている。第2楽章は、穏やかな変奏曲。和声の美しさは特筆に値する。ピアノがオーケストラの一部となって演奏する箇所もあり、この作品が「オーケストラ伴奏付きのピアノ曲」ではなく「ピアノとオーケストラのための作品」であることを印象付ける。第3楽章は華やかさと快活さをあわせ持つ。楽曲の終盤、ピアノ独奏をティンパニが伴奏するあたりは、ベートーヴェンによる楽器の取り扱いの斬新さを象徴している。
ちなみに……ベートーヴェンのピアノ協奏曲は、未完に終わった第6番とは別に、完成している作品がもうひとつ存在する。それは、ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61をピアノ協奏曲に自ら編曲した、ピアノ協奏曲 ニ長調 Op.61aだ。第1楽章では原曲にないカデンツァを新たに書き下ろし、「皇帝」を想起させるティンパニ付きの充実したものとなっている。
ベートーヴェンの「室内楽曲、管弦楽曲、声楽曲編」へ続く。
<文・加藤新平>



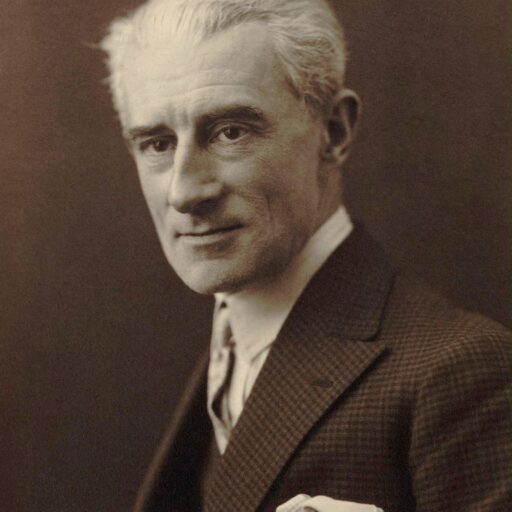

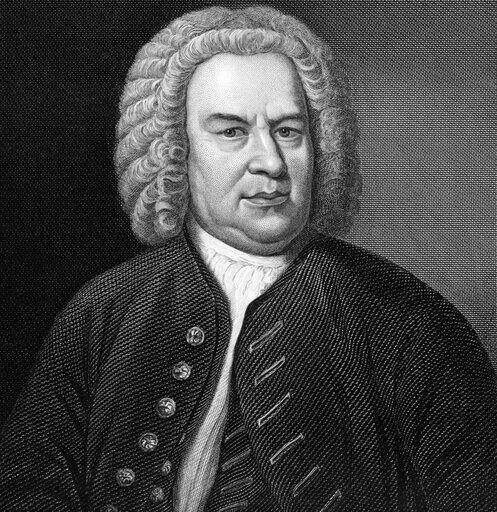







©入り.png)







C福岡諒祠-512x512.jpg)






























