前回はベートーヴェンの“ラズモフスキー・セット”までの弦楽四重奏曲をご紹介しました。今回は、その2年後に作られた作品《弦楽四重奏曲第10番「ハープ」》と《第11番「セリオーソ」》、そしてベートーヴェンが最晩年に取り組んだ至高の弦楽四重奏曲群をご紹介いたします。
対照的な2つの傑作、《ハープ》&《セリオーソ》

ベートーヴェンの肖像画
“ラズモフスキー・セット”の後、約2年間を空けて、ベートーヴェンは《弦楽四重奏曲 第10番「ハープ」》と《第11番「セリオーソ」》を作曲します。2曲とラズモフスキー・セットの間には、《交響曲第5番「運命」》や同じく《第6番「田園」》などの傑作が生まれていますが、この《ハープ》と《セリオーソ》は、まさにこの《運命》と《田園》のように対照的な性格を持ち合わせています。
爽やかで広々とした作品《第10番 変ホ長調「ハープ」》
《第10番「ハープ」》は、1809年に作曲されました。全体的に爽やかで希望に満ち溢れた雰囲気の作品です。第1楽章に印象的なピチカート(弦を指で弾く奏法)でのアルペジオがあり、そこから「ハープ」という愛称が付けられています。また、美しい緩徐楽章である第2楽章でもピチカートがハープを思わせる箇所があります。続く第3楽章は「運命」風の動機がせわしなく押し寄せる疾走感のある曲調で、その後アタッカ(楽章間を切れ目なく続けて演奏すること)で、落ち着いた雰囲気の変奏曲である終楽章へと至ります。
弦楽四重奏版「運命」!?《第11番 ヘ短調「セリオーソ」》
《第11番「セリオーソ」》は、非常に精緻で無駄のない作品。副題の「セリオーソ」は作曲者自身により付けられており、その言葉の意味するところと同じく“厳粛な”作品です。第1楽章は、演奏時間が4分と短い中に非常に密度が濃く詰まっており、その主題の構築性は《交響曲 第5番「運命」》を思わせます。その緊張感と厳粛さは第3楽章まで続きますが、終楽章は雰囲気が一変し、哀愁漂う、メロディックでドラマチックな音楽です。
ベートーヴェン: 弦楽四重奏曲第11番 ヘ短調「セリオーソ」/ Ariel Quartet
ベートーヴェンの行き着いた至高の芸術、後期弦楽四重奏曲
《セリオーソ》のあと、10年以上もの間、ベートーヴェンは弦楽四重奏曲を書きませんでした。ピアノ・ソナタ全32曲も交響曲全9曲も書き終え、残された約2年の人生の間に、ベートーヴェンはさらなる高みを目指すべく、5曲の弦楽四重奏曲を書いたのです。それらは、この上なく美しい反面、実験的で、人を容易に寄せ付けない気難しい部分がありました。ある研究者は、「ベートーヴェンの後期弦楽四重奏曲の後に、そのままシェーンベルクが現れても不思議ではない」と言いますが、それだけ時代の先を行く先進的な作品群だといえるでしょう。
まるでチャイコフスキー!?《弦楽四重奏曲 第12番 変ホ長調》
先ほど、ベートーヴェンの後期弦楽四重奏曲は“気難しい”と書きましたが、いきなり例外です。この《第12番》は、非常に独創的ではあるものの、聴衆を進んで受け入れるような人懐こさがあります。第1楽章の冒頭の和音から、「お、これから何がはじまるんだろう?」とワクワクさせられます。特に第4楽章は非常にウキウキする快活な楽想で、チャイコフスキーの作品を聴いているのかと錯覚してしまいます。
永遠の現代音楽とも言うべき《弦楽四重奏曲 第13番 変ロ長調》-《大フーガ》
ベートーヴェンの後期様式の先進性を語るうえで代表的な1曲です。全6楽章から成る50分近くを要する作品で、なんといっても終楽章に演奏時間が15分を超える巨大なフーガを置いたことで有名です。この大フーガは、冒頭にユニゾン(複数のパートが同じ旋律を演奏すること)で提示されるテーマからして異様で、無調音楽のように聴こえます。続いて冒頭のテーマに基づいたいくつかのフーガとその変奏が展開されていくのですが、グロテスクで異様な印象を受けます。不協和音を伴って走り続ける様子に私は、松井冬子氏の『終極にある異体の散在』という日本画を思い出します。森の中で、鳥や野犬に体をついばまれボロボロになりつつ一心不乱に走り続けている女性の絵で、私がこの曲を知った当時に流行っていた画家であったことからも、その2つが私の中でリンクしているのです。初演当初、難解なこの楽章は聴衆から理解されず、出版の際には新しい終楽章に置き換えられ、もともとの終楽章は《大フーガ》として独立した作品となりました。
この《第13番》は他の5つの楽章も魅力的で、つかみどころのない第1楽章、疾風のような第2楽章、優美さとおどけた感じが同居した第3楽章、ドイツ舞曲風の第4楽章、そして非常に美しい第5楽章“カヴァティーナ”、どこを聴いても魅力的な作品です。
ベートーヴェン: 弦楽四重奏曲 第13番 変ロ長調「大フーガ」/ Quatuor Ebène
暗く陰鬱な難曲《弦楽四重奏曲第14番 嬰ハ短調》
《第14番》は、切れ目なく続く7つの楽章から構成されており、この時点でかなり実験的と言えます。第1楽章は暗く陰鬱なフーガで、この陰鬱さや、答唱(フーガ主題の応答)が完全5度下で現れていくところからも、後のバルトーク《弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽》への影響を窺えます。その後うって変わって快活な第2楽章、接続部的な第3楽章を経て、この作品の中心となる第4楽章の変奏曲へと入ります。こうした長大な変奏曲は、ベートーヴェンの後期様式の特徴の一つであり、後期のピアノ・ソナタや《交響曲 第9番》でも採用されています。その後、かなり風変りなスケルツォである第5楽章、終楽章の序奏的な第6楽章、そしてこの作品で初めて現れる堂々としたソナタ形式の最終楽章で締められます。
人類最高傑作と呼ばれる作品《弦楽四重奏曲第15番 イ短調》
《第15番》は、しばしば“人類最高傑作”と呼ばれます。正確には、その第3楽章に対してです。この楽章は「病癒えた者の神に対する聖なる感謝の歌」という副題が付けられており、リディア旋法によって書かれています。中世のコラールを思わせる、非常に美しい作品です。第3楽章の他にも、第2楽章の中間部での、保続音(特定の声部で和音が変わっても同じ音を長く続けられる=保たれる音)の上で鳴る天国的な高音の旋律や、哀愁漂う終楽章など、魅力の多い作品です。
ベートーヴェン: 弦楽四重奏曲第15番:第3楽章「病い癒えし者の神への聖なる神の歌,リディアの旋法で」 / NAXOS JAPAN(ナクソス・ジャパン)公式チャンネルより
謎に満ちた最後の作品《弦楽四重奏曲第16番 ヘ長調》
ベートーヴェンが残した最後の完成作品ですが、実に不思議な感じのする1曲です。何かを問いかけるような冒頭から、いろいろなパートが組み合わされて一つの旋律が紡ぎ出されます。第2楽章はリズム遊びのようで、中間部には低弦が同じ動きをひたすら繰り返す面白い箇所があります。その後、シンプルなテーマを持った美しい変奏曲が続き、謎の醍醐味ともいえる終楽章にたどり着きます。終楽章の冒頭では、その謎めいた旋律に「Muss es sein ?(かくあるべきか?)」という意味ありげな歌詞のようなものが書かれています。そして、その応答として、快活な第1主題の下に「Es muss sein !(かくあるべし!)」という同じく歌詞のようなものが書き込まれています。ベートーヴェンはこの書き込みで何を伝えたかったのかはわかりませんが、こうした書き込みは、後のシェーンベルクの《弦楽四重奏曲第2番》やベルクの《抒情組曲》など、“歌詞のある弦楽四重奏曲”への布石となっていることは間違いがありません。
これらのベートーヴェンの燦然と輝く至高の弦楽四重奏曲群が立ちはだかってか、続くロマン派では、弦楽四重奏曲の不遇の時代となります。同時代の作曲家、シューベルトも、ベートーヴェンの《第14番》を聴いて、「これ以上我々に何が書けるのだろう」と述べました。
次回はシューベルトの弦楽四重奏曲についてと、弦楽四重奏と弦楽合奏の響きの違いについてご紹介します!
(文・一色萌生)



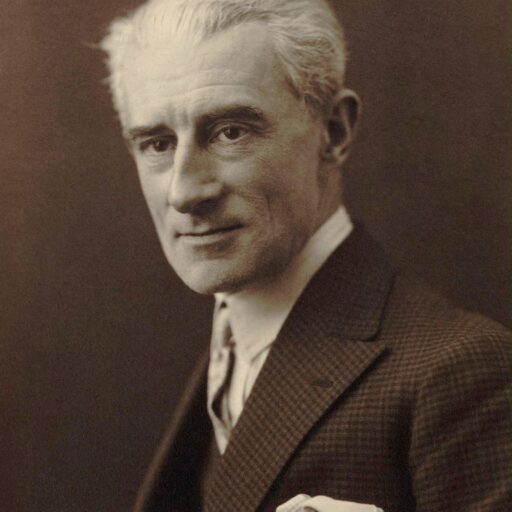

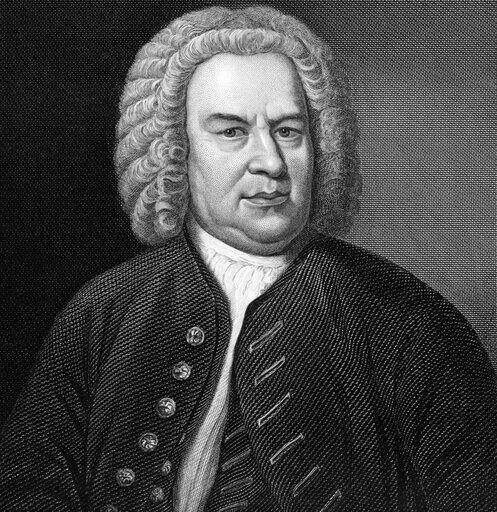







©入り.png)



C福岡諒祠-512x512.jpg)






























