- 引用
- コンサートをより楽しむには、その演奏される曲を理解しておくことが大切。作品が世に出るまでのエピソードや人気の背景を知れば、コンサートがさらに楽しくなることでしょう。そこでスタートした、コンサート・プログラムを簡単に予習する特集企画「Program library」。
Vol.7は「ピアノの詩人」ショパン。世界でもっとも注目される音楽コンクールといっても過言ではない「ショパン国際ピアノコンクール」に名前を冠すなど、クラシック音楽の世界での最重要人物に挙げられます。ショパンが残した数々のジャンルにわたる作品を見てみましょう。
「後編」では、ショパンのピアノ独奏曲のうちスケルツォ、バラード、ピアノ・ソナタなど、室内楽曲、歌曲、ピアノと管弦楽のための作品について紹介していきます。
「前編」からの続き
スケルツォについて
スケルツォとはイタリア語で「冗談」を意味し、日本語では「諧謔曲(かいぎゃくきょく)」とも呼ばれる。とくにベートーヴェンがメヌエットに代わるものとして交響曲に導入したことで知られている。諧謔性を重視し、軽快な楽曲が多い。
一方、ショパンのスケルツォは、「諧謔曲」というより「激情曲」と呼んだ方がしっくりくるほど感情的で、かつ深刻な曲調である。
一方、ショパンのスケルツォは、「諧謔曲」というより「激情曲」と呼んだ方がしっくりくるほど感情的で、かつ深刻な曲調である。
《スケルツォ第2番》変ロ短調 Op.31は1837年の作品であり、低音のつぶやくような音形と、高音で唐突に鳴り響く和音の対比による開始が印象的であり、ショパンの書いたスケルツォの中ではかなり明るい部類に属する。中間部にコラールを置いていることも独特。
1839年に書かれた《スケルツォ第3番》嬰ハ短調 Op.39は、拍子も調性もあいまいな序奏と、機動性を重視した主題に始まるソナタ形式の作品で、技巧の充実ぶりと変化に富んだ曲調から、さながら「単一楽章のピアノ・ソナタ」ともいうべきものとなっている。
バラードについて
バラードは、12世紀に吟遊詩人の歌う抒情歌の形式として現れ、詩のジャンルと歌のジャンルのそれぞれで定着したものであった。このバラードを器楽曲のジャンルに導入した先駆者が、ほかならぬショパンである。
1831年から1835年にかけて書かれた《バラード第1番》ト短調 Op.23は、オペラのレチタティーヴォを思わせる序奏、主部の悲しいワルツ風の第1主題、讃歌風の第2主題、いずれも圧倒的な旋律美で聴く者の胸を打つ。
《バラード第2番》ヘ長調 Op.38は、牧歌風なヘ長調の部分と、激情的なイ短調の部分とがせめぎ合う作品である。
《バラード第3番》変ホ長調 Op.47は、1840年から1841年にかけて書かれたもので、半音階的で美しい、ややオーケストラ風の主題に始まり、軽快な主題やめまぐるしく動く左手の上で悲痛に歌われる主題が絡み合い、華々しい終結へ向かっていく。
《バラード第4番》ヘ短調 Op.52は1842年に書かれた作品で、序奏つきのソナタ形式であるが、変奏曲の技法も採り入れられ、ショパンの技巧が尽くされている。ハ長調の穏やかな序奏に続いて、短調と長調を行き来する不安定なワルツ風の第1主題、美しい歌謡風の第2主題が提示され、徹底的に展開される。ピアノ協奏曲のカデンツァを思わせるフレーズを経て、静かにコラールが響くと、半音階的で激しいコーダへと突入し、破滅的な終結を迎える。
ピアノ・ソナタについて
ショパンは生涯にピアノ・ソナタを3曲残した。これは彼のピアノ独奏曲に占める数としてはごく少ないものである。
ピアノ・ソナタ第1番 ハ短調 Op.4は、1828年、ワルシャワ音楽院在籍中に書かれた作品で、古典的な4楽章形式を踏まえた習作として書かれているが、転調のみごとさや、第3楽章でポーランド風の5拍子のワルツを書いていることなど、見るべき点も多い作品である。
ピアノ・ソナタ第2番 変ロ短調 Op.35は、1839年にノアンで完成した作品である。陰鬱な序奏に始まる第1楽章は、急き立てられるような第1主題が再現部に現れず、明るい第2主題が再現部を支配するという独特の手法を採っている。第2楽章は荒々しい主部と穏和なトリオの対比が印象的。そして第3楽章は有名な〈葬送行進曲〉である。この楽章を管弦楽編曲したものはショパンの葬儀でも演奏された。第4楽章は、両手がユニゾン、調性も不安定、大規模なソナタの終楽章でありながら2分足らずであっという間に終わるという、異例尽くしの音楽である。「ソナタ」という形式に対してショパンが叩きつけた挑戦状と言えるかもしれない。
1844年に書かれたピアノ・ソナタ第3番 ロ短調 Op.58は、第2番とは打って変わって古典的な多楽章ソナタの形に立ち戻っている……かのように見える。しかし、第1楽章の再現部において第1主題を省略し、ノクターン風の第2主題に重きを置く書法はやはりショパンの革新性を示している。独立した楽曲としての「スケルツォ」では深刻さばかり際立っていたショパンが、このソナタの第2楽章ではめずらしく諧謔性(かいぎゃくせい)に富んだ軽快なスケルツォを書いている。第3楽章は、まさしく夜想曲と呼ぶべきもの。そして第4楽章は、運動性を重視しつつも力強く半音階的な旋律で押してゆくフィナーレ。ピアノ協奏曲風のかけ合いも多用され、ロ長調で堂々たる終結を迎える。第2番のような挑発的な姿勢は抑えつつ、堅実な書法でまとめられており、ショパンの作品の中でも最上位に位置する名作である。
その他のピアノ独奏曲について
《24の前奏曲》Op.28は、1839年にマヨルカ島で完成した。この作品はショパンがJ.S.バッハの《平均律クラヴィーア曲集》を意識して作曲したものであると言われている。ただし、バッハがハ長調-ハ短調-嬰ハ長調-嬰ハ短調……という同主調関係に基づく配列を採用しているのに対して、ショパンはハ長調-イ短調-ト長調-ホ短調……という平行調関係と五度圏に基づく配列を採用している。悲しげな第4番ホ短調、そして明るく歌謡風で某胃薬のCMでも有名な第7番イ長調など、名曲ぞろいの作品である。
《幻想曲》Op.49は、1841年に完成した作品で、自由な形式で書かれることも多い「幻想曲」というジャンルで、あえてソナタ形式を採用している。しかし、古典的な枠組みにはめ込んだというわけではない。葬送行進曲風の序奏に続いて、3連符を多用した幻想的なヘ短調の第1主題、切迫感のある変イ長調の第2主題、軽快な変ホ長調の第3主題、そして讃歌風で同じく変ホ長調の第4主題が次々と提示される。主題が4つあり、通常のソナタ形式以上に変化に富んでいることが、本作が「幻想曲」たる所以であるかもしれない。
1846年に完成した《舟歌》Op.60は、左手のたゆたうような音形の上で嬰へ長調の旋律が歌われる形で始まり、ショパンお得意の転調を重ねてゆく。ロマン派の時代の「性格的小品」にありがちな《舟歌》というタイトルを持ちながら、技巧的には難曲でもある。
ショパンの室内楽曲について
ショパンは生涯に3曲の室内楽曲を残した。1828年に作曲した《ピアノ三重奏曲》Op.8、1831年に発表されたチェロとピアノのための《序奏と華麗なるポロネーズ》Op.3の2曲は青年期の作品である。
一方、1846年に書かれたチェロ・ソナタ ト短調 Op.65は、チェリストで親友のオーギュスト・フランショームのために書かれたもので、ショパンにとって生前最後に発表・出版された作品となった。叙情的で息の長い第1主題と半音階的でロマンティックな第2主題が対比される第1楽章、軽快なスケルツォの第2楽章、ピアノとチェロが「うた」を紡ぐ第3楽章、そしてイタリアの舞曲「タランテラ」を想起させる情熱的なフィナーレという4つの楽章から成り立っている。チェロとピアノが対等の関係にあり、どちらのパートにも高い技巧が求められている。ショパンが決して「ピアノだけの作曲家」ではないことを示す傑作である。
ショパンの歌曲について
ショパンは生涯にわたって歌曲を作曲した。しかしこれらの作品は公開演奏も出版も前提としない私的な作品であったため、一部の作品を除いて生前には出版されず、死後《17のポーランドの歌》Op.74として1857年に出版された。
《17のポーランドの歌》の歌詞はいずれもポーランド語であり、アダム・ミツキェヴィチをはじめとするポーランドの詩人の作品から採られている。第1曲〈願い〉ではマズルカのリズムが活用され、第9曲〈メロディ〉では巧みな転調がきかれる。第10曲〈闘士〉におけるファンファーレなど描写的な要素もショパンの歌曲には随所にみられ、第17曲〈舞い落ちる木の葉〉では、ピアノの旋律に無伴奏の歌が応える開始に続いて、抒情的な旋律や凱歌風の旋律、葬送曲風の旋律が次々に現れるなど、4分程度の作品の中にさまざまなドラマがある。
ちなみにこの曲は、ポーランドの「11月蜂起」失敗を悲しんで書かれたものとも言われている。
ちなみにこの曲は、ポーランドの「11月蜂起」失敗を悲しんで書かれたものとも言われている。
ショパンのピアノと管弦楽のための作品について
ショパンのピアノと管弦楽のための作品は、すべて1830年以前、つまりポーランド時代に書かれている。1827年に書いた《ラ・チ・ダレム変奏曲》Op.2は、1829年のウィーン・デビューの際に初演されて大好評を博し、シューマンが『新音楽時報』誌上で「諸君、脱帽したまえ。天才だ!」とショパンを絶賛したことでも知られている(なお、ショパンはシューマンによるこうした持ち上げ方にかなり困惑していた模様)。
1829年から1830年にかけて書かれたピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 Op.21は、出版順序の関係で番号が繰り下がっているが、ショパンにとって初のピアノ協奏曲であり、ワルシャワでのプロ・デビューを飾った作品でもある。第2楽章中間部のレチタティーヴォを模した激しい部分からは、オペラ愛好家としてのショパンの一面がうかがえる。マズルカを採り入れた第3楽章中間部における、弦を弓の木の部分で叩く「コル・レーニョ」の指示は、ショパンのオーケストラについても優れた発想を持っていたことを示している。
1828年に完成した《ポーランド民謡による大幻想曲》Op.13は、序奏、アンダンティーノ、アレグレット、ヴィヴァーチェの4つの部分からなり、アンダンティーノ部分ではポーランド民謡《もう月は沈み》が夜想曲風に登場し、アレグレット部分ではポーランド民謡《カロル・クルピンスキの主題》が引用される。ヴィヴァーチェ部分はポーランドの民族舞曲《クラコヴィアク》で一気に駆け抜ける。
同じく1828年に書いた《ロンド・クラコヴィアク》Op.14は、ホルンの空虚五度の和音の上でピアノがマズルカを歌い上げる幻想的な導入部に始まり、ピアノと管弦楽の掛け合いがみごとな「クラコヴィアク(※ポーランドの舞曲のひとつで、馬の動きを模した急速な2拍子の舞曲)」部分が続く構成で、ショパンの作品としては比較的管弦楽部分もよく書けていると評されている。
1830年に書かれたピアノ協奏曲第1番 ホ短調 Op.11は、同年10月11日、ワルシャワでの告別演奏会で初演された。1832年のパリ・デビューの際にも演奏して好評を博した作品である。力強い第1主題と、歌謡風の第2主題の対比がみごとな第1楽章、ロマンティックな第2楽章、そして「クラコヴィアク」のリズムを取り入れて熱狂的に盛り上がる第3楽章からなる本作は、ショパン・コンクールのファイナルで多くのピアニストに選ばれるのもうなずける充実した作品である。
賢明な「ららら♪クラブ」読者のみなさまはお気づきだろう。「アンスピ」は一体いつ出てくるのか……? と。
《アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ》Op.22は成立の経緯が複雑であり、まず1831年に管弦楽とピアノによるポロネーズ部分が作曲され、1834年にピアノ独奏の「アンダンテ・スピアナート」が追加された。そして現在では、1836年に原曲と合わせて出版された、ショパン本人の手によるピアノ独奏曲編曲版のほうが有名となっている。透明感のある「アンダンテ・スピアナート」部分と、華やかなポロネーズが好対照を成しており、ショパンの書いたポロネーズの中でも《英雄ポロネーズ》と並ぶ傑作である。ピアノ独奏版に触れる機会が多いが、管弦楽伴奏版も案外悪くないので、ぜひ一度試しに聴いてみていただきたい。
《アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ》Op.22は成立の経緯が複雑であり、まず1831年に管弦楽とピアノによるポロネーズ部分が作曲され、1834年にピアノ独奏の「アンダンテ・スピアナート」が追加された。そして現在では、1836年に原曲と合わせて出版された、ショパン本人の手によるピアノ独奏曲編曲版のほうが有名となっている。透明感のある「アンダンテ・スピアナート」部分と、華やかなポロネーズが好対照を成しており、ショパンの書いたポロネーズの中でも《英雄ポロネーズ》と並ぶ傑作である。ピアノ独奏版に触れる機会が多いが、管弦楽伴奏版も案外悪くないので、ぜひ一度試しに聴いてみていただきたい。
ショパンの作品の聴きどころ
ここまで、ショパンの生涯と作品を簡単にご紹介した。
ショパンの作品といえば、やはり超絶技巧を凝らしたピアノ書法に耳を奪われるだろう。しかし本稿では、ショパンがライフワークとして書き続けたマズルカやポロネーズのリズムが、ピアノ協奏曲をはじめとするさまざまな作品にも顔を出していることこそが、第一の聴きどころであると強く主張したい。ショパンは、それまでクラシック音楽の表舞台に出てくる機会のなかったポーランドの民族音楽を、芸術音楽へと昇華させたのである。
バグパイプのような空虚五度を好む和声、そして音階の4番目の音を半音上げる独特の音感覚も、ポーランドの民族音楽からショパンがつかみ取ったものである。
ショパンの作品といえば、やはり超絶技巧を凝らしたピアノ書法に耳を奪われるだろう。しかし本稿では、ショパンがライフワークとして書き続けたマズルカやポロネーズのリズムが、ピアノ協奏曲をはじめとするさまざまな作品にも顔を出していることこそが、第一の聴きどころであると強く主張したい。ショパンは、それまでクラシック音楽の表舞台に出てくる機会のなかったポーランドの民族音楽を、芸術音楽へと昇華させたのである。
バグパイプのような空虚五度を好む和声、そして音階の4番目の音を半音上げる独特の音感覚も、ポーランドの民族音楽からショパンがつかみ取ったものである。
そして、クラシック音楽ファンの方には「ええっ?」と思われるかもしれないが、ショパンのピアノと管弦楽のための作品では、管弦楽にこそ注目して聴いてほしい。
「管弦楽の扱いが下手! シューマンやブラームスやグリーグの作品と比べると響きが貧弱!」と非難されることの多いショパンであるが、これはそもそも、ショパンをはじめとする19世紀のコンポーザー・ピアニストの多くが書いていた「管弦楽伴奏付きのピアノ曲」と、シューマンやブラームスが書いた「ピアノ独奏付き交響曲ともいうべきシンフォニックな曲」との、ジャンルの違いを考慮していない論である。このふたつは「ピアノと管弦楽」という形態こそ同一であるが、作品の性質を安易に同一視することはできない。
確かにショパンは管弦楽の扱いに慣れておらず、他人の手を借りて管弦楽を書いていたと言われている。しかし、例えばピアノ協奏曲第2番における「コル・レーニョ」や、《ロンド・クラコヴィアク》冒頭のホルンの用法など、聴き手をあっと言わせるアイデアマンの一面も持っており、「下手」の一言で片づけるには惜しいものがある。
また、室内楽曲や歌曲も近年再評価が急速に進んでいる。「ピアノの詩人」というイメージだけでなく、少々先走った言い方にはなるが、自身の生まれた国の民族音楽と民族性に立脚して芸術音楽を書いたという点で、「国民楽派の先取り」ととらえたほうが、よりショパンへの共感と理解は深まるのではないだろうか。
<文・加藤新平>





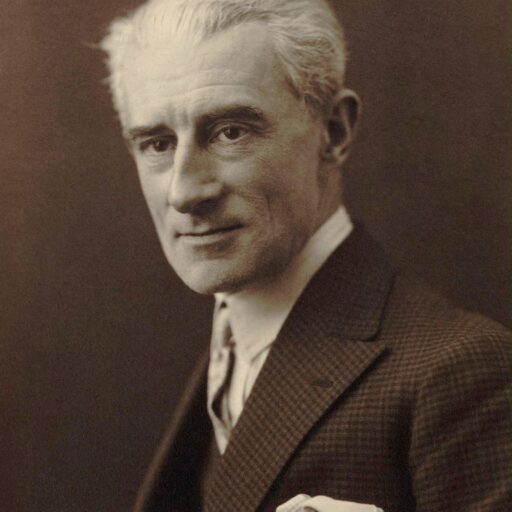

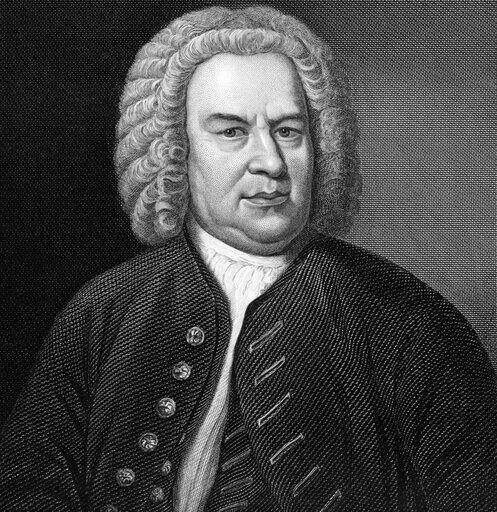






©入り.png)






C福岡諒祠-512x512.jpg)






























